1.はじめに
東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所の事故から6年9ヶ月が過ぎようとしている。避難指示が解除になっても、さまざまな理由で自宅に戻ることができない人は多く、住まいの再建ができないままの人もいる。
震災前、福島を拠点にユニバーサルデザインのまちづくりを目指すNPOを設立し運営に携わってきた。建築士として施設や建物のユニバーサルデザインへの提言だけでなく、耳や言葉の不自由な方や高齢者のためのコミュニケーションツールの開発なども行うなど、誰もが暮らしやすいまちづくりを目標に活動をしてきた。しかし、原発事故によってその活動は大きく変わった。暮らしやすいどころか、住まいを追われる何万もの人々を目にすることになるのである。
震災から約3ヶ月後、応急仮設住宅の入居が始まると、「仮設住宅はユニバーサルデザインであると思い込んでいたが、バリアがたくさんある」という声が耳に入った。仮設住宅では、ある程度プライバシーも確保できるため、体育館や公共施設などの「避難所」とは比べものにならないはずである。しかし、入居できることが決まってほっとしたのも束の間、狭い上に収納も少ない、段差も多く音も筒抜け、といった声が広がり始めたのだった。しかし、当時の私たちは自分の生活を立て直すことで精一杯であった。原発事故によって、浜通りのみならず中通りにも「放射能汚染」という大きな影響が及んでいたからである。およそ半年が過ぎたころ、やっと調査に着手できる目途がついた。そして2011年10月から3ヶ月にわたり、県内7市町村、計10ヶ所の応急仮設住宅地を調査、『これからの仮設住宅への福島からの提言・応急仮設住宅のUD調査から見えた現状と問題点』(特定非営利活動法人ユニバーサルデザイン・結(ゆい)発行 2012年3月)をまとめた。(写真1)(図1)
この調査では、実にさまざまな人々との出会いがあった。応急仮設住宅地を訪れ住戸内を実測し、自治会長、管理人、そして居住者への聞き取りを行った。その聞き取りから、生活環境のさまざまな問題点が明らかになり、問題解決のための取り組みも浮かび上がってきた。その調査からもすでに6年が経とうとしている。いま改めて、応急仮設住宅地で出会った人々の懸命な姿を振り返り、現在の、そしてこれからの住まい再建のゆくえを考えてみたい。
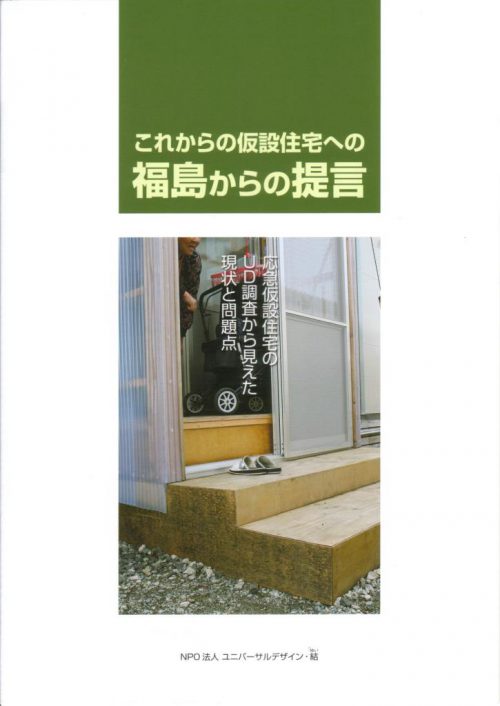
写真1)

図1)県内の応急仮設住宅地と入居人数
(『これからの仮設住宅への福島からの提言』より)
2.仮設コミュニティの実態
・障がいのある人者や高齢者への対応
当時、震災と原発事故の影響で避難せざるを得なかった人々は、複数の避難所を経てやっと仮設住宅や借り上げ住宅に入居したという人がほとんどだった。避難所や親戚宅、知り合いのところなどを転々とした回数が5回から7回に上る人もいた。一度県外へ出て戻ってきたという人も多く、その過程では食料やガソリンなどの燃料不足の中、受け入れてくれる避難所を探して彷徨い歩いたという人さえいる。そんな中、一日も早く落ち着いた暮らしをするため、国が建設する「災害時応急仮設住宅」には大きな期待がかけられていた。
仮設住宅への入居は、入居の時期が早ければ早いほど「自分の身体能力に見合った住戸を選ぶことができない」という実態であった。まず、入居は今まで住んでいた市町村を通じての抽選で、抽選に当たるまでは避難所での生活を続けなければならない。さらに、高齢者や障がいのある人の優先的入居は自治体の対応がまちまちな上、高齢者や障がい者向けの「バリアフリータイプ」と呼ばれる住戸の設置がないところもあり、最終的に全体の10%ほどの設置であった。しかも、高齢者が多い地域からの避難にもかかわらず、高齢者や障がいのある人のための部屋は5~6世帯ほどの長屋に1世帯分を配置するというもので、ベッドを置けば身動きができない、車いすでは部屋の中を移動するのもやっと、玄関から入ることすらできないところもあった。
南相馬市では、心身に障がいがあり車いすを使う40歳代の娘さんとふたりで暮らす70歳代の女性に出会った。「抽選に当ったから」と入居したプレハブ型仮設住宅は傾斜した土地に建っているため、入居した部屋は玄関から室内まで70cmもの段差があり、車いすでの外出などは自力では無理な状態だった。母親も足が悪く、片足を引きずるように歩いていた。(写真2) 震災以降、障がいのある娘さんがデイサービスを利用できるのは週に一度だけとなり、その日はデイサービスの職員が玄関にスロープをかけて介助してくれるので外出できるが、他の6日間は家に閉じこもったままだった。仮設住宅の浴室は入り口に段差があるため利用できず、デイサービスの日に入浴するだけだという。当時娘さんは、自分が置かれている状況や将来を悲観し、「死にたい」という言葉を口にするようになったと母親は途方にくれていた。バリアフリータイプの住戸の設置がない住宅地だったが、せめて段差の少ない隣の棟の端の部屋に入居することができれば、この親子の生活はもっと違ったものになっていたかもしれない。(写真3)

写真2)入口の段差 高さは計70㎝になる

写真3)隣棟へ行くほど入口の段差は小さくなる
・高齢者の暮らしを守る
どの仮設住宅地にも言えることであるが、高齢者だけで暮らしている世帯や単身の世帯がとても多い。いわき市に避難をしている広野町の自治会長さんを訪ねた。ここも65歳以上の高齢者の多い仮設住宅地で、できるだけ同じ地域に住んでいた人で構成されるように町が配慮をしたということだったが、それでも知らない人もいるという。自治会長は「この仮設住宅地からは、阪神淡路大震災の時に問題になった孤独死は、一件も出したくない」と、毎日お年寄りや一人暮らしの方々を訪ねては声をかけていた。すでに、昼間でもカーテンを閉め切っている気になる世帯があると言い、声かけを行って地域全体で住民を守ろうと努力していた。原発事故直後の混乱から、従来の集落ごとに避難できたところはほとんどない。しかも、仮設住宅の入居は抽選であるため、新しいコミュニティをいちから作り上げる作業が必要だった。最初は知らない者同士でも、支えあって生活しようと必死だったことがうかがえる。
・広い家から狭小の仮設住宅に
伊達郡桑折(こおり)町にある「桑折駅前仮設」で出会った浪江町自治会長だった小澤さんは、建築士であり入居当初から仮設住宅の現状を県やメディアなどに訴えてきた。浪江町の方々は、ほとんどが原発事故の被害による避難生活だったが、ちょうど調査に入った日には、断熱材の追加や窓を二重にするといった寒さ対策が急ピッチで行われていた。(写真4)(写真5)設置されて5ヶ月あまり、プレハブの住戸内部は結露がひどくカビも繁殖していた。夏の暑さも耐えがたかったが、冬の寒さにも耐えられるか不安だと語っていた。その仮設住宅に住む方々からは、「出入り口(後付けの風除室)を「玄関」と呼ぶのはやめてほしい。これは「玄関」といえるものではない」と苦言を呈された。その風除室の屋根は強風で飛ばされることがあり、何回も補修をしているという。また、「設計者も住んでみれば、調査するまでもないのでは」と、建築の仕事をしている者には厳しい指摘もあった。
震災や原発事故前までは、避難をしているほとんどの人が広い「持ち家」に住んでいた。福島県の農村部の特徴として、代々続く家を守りながら子や孫と同居をする形が多い。三世代同居となると古い家も新しい家も、50坪から70坪といった面積の大きなものになる。ところが、避難先で入った仮設住宅の大きさは10坪程度である。「今まで70坪の広い家に住んでいたのに、10坪の家に住まなければならなくなった現実をどう受け止めたらいいのか」と言った住民の言葉が忘れられない。
さらに、それまで同居していた家族がばらばらになるケースも少なくない。応急仮設住宅は、国の災害救助法により一戸あたりの面積に規制がある。部屋数の少ない仮設住宅では三世代同居が叶うはずもなく、若い世代は借り上げ住宅へ、高齢者は仮設住宅へと離れて住む例も多く、「一緒に暮らしていた孫に、たまにしか会えなくて寂しい」と訴える人もいた。

写真4)桑折駅前仮設

写真5)断熱化工事中
3.生活支援とコミュニティ
・支え合いのしくみをつくる
仮設住宅地での支えあいは居住者の間だけとは限らない。避難自治体とともに受け入れ自治体でも生活支援体制が構築された例を紹介したい。前述の浪江町の住民が暮らす「桑折駅前仮設」では、受け入れ自治体である桑折町と浪江町がさまざまな協力体制を構築して避難者の生活を支援した。その中心となったのが、両町と福島県北地域で公益活動を行うNPOなどが立ち上げた「伊達桑折×双葉浪江=交流と賑わいづくり応援プロジェクト連絡協議会」である。
ここは、旧福島蚕糸工場跡地を桑折町が提供することによって、浪江町のために286世帯分の仮設住宅が用意された。希望者による抽選は浪江町当局によって行われ、2011年6月から入居が始まった。この住宅地にはもともと桑折町内に居住し、震災によって自宅が全壊した14世帯も入居しており、共同で自治会を設立し運営をしていた。避難住民が受入れ町民と交流すること、つまりはご近所付き合いをすることによって、できるだけ避難以前に近い生活をしようというものである。農産物を直売する「軽トラ市」を開いたり、共同のカフェを設置したりと交流の場が広がるとともに、就労と生きがいの場の提供につながった。また、支援のNPOが発行する「おたがいさま新聞」(写真6)は、他の仮設住宅地に住む浪江町民を含めた交流促進と情報発信の源となった。現在も「おたがいさま新聞+ぷらす」として発行が続けられ、避難を続ける住民同士や受入れ自治体の人々とをつないでいる。
もうひとつは、原発事故による計画的避難指示により集団避難をした飯舘村の例である。先にも述べたように、仮設住宅地の一番の特徴は高齢者が多いことである。飯舘村から避難している30世帯が暮らす「福島市飯野町明治仮設」(写真7)では、住民の特徴や人間関係が一目でわかる「支えあいマップ」(写真8)を作成していた。一人暮らしのお年寄りや障がいのある人を把握し、助け合う仕組みをつくるというものだ。どの世帯とどの世帯が親戚関係にあるといった情報や、高齢者を介護している世帯であるといった情報があれば、いざというときに助け合うことができ、仕事で留守がちな住戸にも気配りをすることができる。
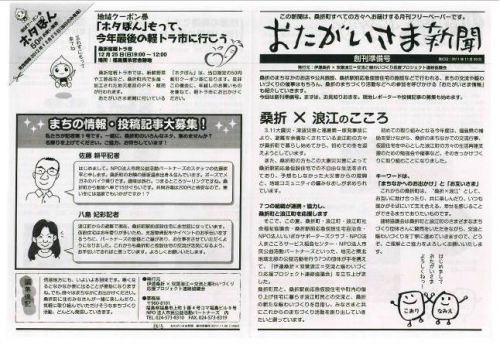
写真6)おたがいさま新聞
(認定NPO法人市民公益活動パートナーズ発行)

写真7)福島市飯野町明治仮設

写真8)支え合いマップ 新聞記事
(朝日新聞2012年11月10日付)
・女性の力を活かす
聞き取りをさせていただいた自治会の会長は、当時はほとんどが男性であった。やはり仮設住宅地でも先頭に立つのは男性なのか、という印象を受けた。そのような中、「あの村らしい」と思える取り組みを飯舘村の仮設住宅で目にした。飯舘は「若妻の翼」という若い妻たちのために海外研修を行ってきた村である。
飯舘村の10ヶ所の仮設住宅地には、7人の「管理人」と呼ばれる人がいた。ひとつの仮設住宅地に一人、規模によって2つを兼務している例もあった。「管理人」はほとんどが女性で、イベントの企画や家庭訪問、自治会と連携し防犯活動や住民の引きこもりを防ぐなどの役割を担っていた。月に一度、県北地域や相馬市など広い範囲に点在する仮設住宅地から7人が集まり、情報交換する場もあるということだった。
前述の「支えあいマップ」を作成したのも、もちろん女性の「管理人」が中心になった。高齢者宅へは毎日訪問し声掛けを行っていたため、浴室で動けなくなっていた高齢の男性を助けることができたという。また、父子家庭の子どもには、学校から帰る時間に声をかけるなど細やかな気配りをしていた。さらに、水道管の凍結や雨樋の修理の手配など、その仕事は多岐にわたっていた。
福島市松川町の仮設住宅地の管理人は、家に引きこもっていた高齢の女性に何とか元気になってもらいたいと、女性の得意だった着物をほどいて小物に仕立て直す事業を立ち上げた。その女性も自分の役割を見つけて元気になった上、今では大手百貨店と提携するなど、首都圏にも発信するまで事業が拡大した。そして、避難が解除になって村に戻った時も、事業を継続できるようなしくみを整えておきたいと語っていた。
このような女性の「管理人」というしくみは、飯舘村のように小規模な自治体だからできるといえるかもしれない。しかし、孤独死や事故、事件を未然に防ぐのには有効であったことは確かであり、避難先でのコミュニティの構築において女性の力が発揮された例だといえる。
4.おわりに―住まいの再建へ向けて
これから、住まいをどう再建していくかは、大きな課題である。復興公営住宅の建設も進んだが、住戸は単身者や核家族向けの形態であるため、家族数の多い避難者世帯の選択肢からは外れがちとなる。そのため、自宅を避難先に自主再建せざるを得ない例が多い。
避難指示が解除され、自宅の補修をして帰還した世帯もある一方、何年も放置せざるを得なかった住宅の荒れ様に帰還を諦める人も多いと聞く。留守の間にイノシシなどの野生動物に占領されてしまっている光景は言葉を失うほどである。現在も仮設住宅に残っている人は、さまざまな事情から生活再建にふみ出せない高齢者が多い。今後、「帰りたくても帰れない」人を、どう支援していくかが問われている。
いつ起こるかわからない災害。福島県のように原発事故も重なって、このよう過酷な状況をつくりだすことは、二度とはあってはならないと強く思う。平成31年3月末には応急仮設住宅の供給が原則終わる予定(県は帰還困難区域からの避難世帯については個別に対応する)であるが、震災から実に8年の月日が経つことになる。しかしそれまで、どのように住民の暮らしを支援していくかが重要になってくる。被災者が「前を向いて自立していくための支援」が求められているのである。
震災を経て、「ユニバーサルデザイン」とは何か、改めてその意味と意義を突きつけられたような気がしている。緊急避難という状況下で、心身ともに傷ついた人々を包む住まいが応急仮設住宅である。だからこそ、この教訓を活かし従来の仮設住宅の考え方を再考し、「最低限の快適さ」は保障されなければならない。多様な人々のことを想定し、誰もが使いやすい「もの」や「まち」、合理的なしくみやサービスを考えておくというのがユニバーサルデザインである。「災害時応急仮設住宅」とその「しくみ」、そして「支援のしくみ」を含めてユニバーサルデザインであるべきで、それは、またいつ来るかわからない災害に備える有効な手段にもなるはずである。


最近のコメント