2016年6月30日収録@日本建築学会会館
日埜直彦×浅子佳英×吉本憲生(司会)×市川紘司(司会)
■表参道の特殊性

《アップルストア表参道店》を南西側からみる。以下、特記なき写真は、司会撮影。

《アップルストア表参道店》を西側からみる。
市川紘司:はじめに《アップルストア表参道店》(以下、《アップル》)を取り上げる経緯についてお話しますが、まずは基本的な建築情報をおさえておきます。
《アップル》は2014年に竣工した建物で、設計はペンシルバニアの建築事務所ボーリン・シウィンスキー・ジャクソン、日本のローカルアーキテクトとして光井純さんの事務所が入られています。地下一層、地上一層からなる構成で、地上階は高さ10m、奥行き12m、幅が30mほどで三面ガラスファサードの大空間になっており、表参道という一等地にもかかわらず、容積率をすべて使わずに抑えているのが特徴です。通りからだと非常にシンプルなガラスボックスに見えますね。非常に洗練されたモダニズムの美学のようです。しかし近くにある歩道橋から見ると、ガラスの上に先細りした軒をもつ屋根が載っていて、奥に控える壁からちょうどアップルのラップトップ型PC(=屋根)が開いたような、いわばアイコン建築でもあることが分かります。
それで、なぜこの《アップル》を建築作品小委員会の特集で取り上げるのかというと、昨年中国留学から帰ってきて表参道を久しぶりに歩いたとき、これを見て妙に新鮮な驚きを個人的に感じたからなんですね。その日は《イザベルマラン表参道店》を見ようと友人の建築家と来ていたのですが、これとの落差も大きかった。それと何より、表参道を歩く人たちが《アップル》を見て、そのガラスの大きさだったり透明性だったりに素朴に驚いているのが面白かった。表参道に建ちならぶ《TOD’S》などの奇抜な外装表現のアイコン的建築よりも、ベタに「ガラスが大きくて透明!」ということのほうが衆目を集めている…——いま考えればこれは《アップル》が竣工したてだったからに過ぎない気もしますが、ともかく、そのような感受性があるとするならば、色々と考えてみたいなと思ったのです。そこで今回は、東京という都市と建築とインテリアにお詳しい日埜直彦さん、そして浅子佳英さんにお話を伺いたいと思った次第です。
私が最初に思ったのは、端的に言ってしまえば、《アップル》は、レム・コールハース(OMA)が《ドバイルネッサンス》でやろうとしたことだ、というものでした。《ドバイルネッサンス》は、アイコン建築の聖地ともいえるドバイの中心に、形態的特徴を排したシンプルな高層建築をつくることを提案したものです。アイコン建築だらけの場所では、反アイコン的な単純形態の建築こそが逆説的にアイコンになる。OMAの設計主旨はこのようなものだったかと思います。《アップル》も期せずしてそのようなものになっているように思うのですね。《アップル》を成り立たせる技術やコストの異常さというのは設計実務をやっていない私からも想像がつきますが、ともあれ表参道を歩く一般の人の目線からすれば、それは「ガラスでシンプルにつくられた形態」でしょう。奇抜さを装わないことで奇抜になっている。ミニマルな表現を突き詰めたがゆえにそれが反転してアイコン建築になる。そのような異化効果が生まれているように思います。

会場写真
日埜直彦:「地」としてのアイコン建築がたくさんある表参道だからこそ、《アップル》が「図」として見えてくるのが興味深い、ということですね。まずは表参道という場所の特質について、東京の歴史的文脈を押さえておくのが良いんじゃないでしょうか。
明治神宮ができる以前の原宿、表参道は農村でした。この歴史の浅さのため土地所有が比較的細分化しておらず、現在でも数百坪のいわゆる旗艦店を独立店舗として成立させるのにちょうど良い大きさの土地があります。同様にブランド・ショップが建ち並ぶ銀座などとは条件が異なるわけです。
さらに1990年代以降、REIT(リート)や不動産の証券化が一般的になり、建築を建てる際に国内外のさまざまな資本が入ってくるようになったことも、今日のアイコン建築が建ちならぶ状況をかたちづくった要因です。そうしたREITなどによる建築プロジェクトの企画において、知名度のあるブランドの独立店というスキームは、企画のコンテンツとしても投資を誘引する打ち出し方としてもわかりやすい。そういう不動産投資のスキームの変化があれらの建物を成立させています。「原宿」という地名のアジア圏におけるネームバリューも、そうしたアジアからの投資を引き込む上で効いているでしょうね。
これらの要因が揃うことで、現在の表参道にブランドカラーを前面に打ち出した独立店舗建築、つまりアイコンビルが「地」をなすように建ちならぶようになったわけです。これは世界的に見てもかなり特殊な状況でしょう。他のアジア都市の場合、ショッピングストリートに面する大型商業ビルのテナントとしてブランドショップがつくられ、各ブランドはそれぞれ派手なファサードをつくるけど、建物自体を建てるという発想にはならない。ヨーロッパ・アメリカの場合は、古典的な街並への景観的な配慮から建物の外観そのものにブランドカラーを打ち出すことはそもそも難しく、既存の建物のファサードの背後に隠れて店舗は出来る。
私自身も表参道沿いでアパレルブランドのフラッグシップストアのインテリアデザインをやっていますけど、原宿という場所は世界的に見ても独特の意味合いがあると思います。

表参道沿いに位置する《F.I.L. TOKYO》(店舗設計 日埜直彦氏) 撮影 平井美行
浅子佳英:地という意味では、まさに表参道という道そのものもこのエリアを特殊にしている要因のひとつですね。美しいケヤキ並木があり、車道と歩道の幅がそれなりに確保されているからこそ、通りからそれぞれのアイコン建築を引いて眺めることができるからです。
それから、戦後にワシントンハイツがつくられたことも、外国人向けブランドが増えた理由としてしばしば指摘されます。たとえばキディランドは、もともとは「橋立書店」という書店が木製の玩具を置いたところ外国人に受け、おもちゃ屋になったという経緯があります。このように、外国人向けのお店、そしてそれらの西洋の文化を欲する国内の一部の人々が集まる場所という、商売として成立する下地があり、表参道一帯は徐々にファッションストリートとして発展を遂げていきました。
ただ、イッセイミヤケ、ヨウジヤマモト、コム・デ・ギャルソンなどの日本のブランドショップはもともと原宿側ではなく根津美術館側に集まっていて、現在のように外資系の大型ブランドが入り込むようになったのはおもに1990年代以降のことです。僕の記憶が正しければ、1998年にリカルド・ボフィルによる《青山パラシオタワー》のなかに《グッチ》の大型店ができ、それ以降の4〜5年のうちに一気に様変わりしていきました。
吉本憲生:表参道の交差点より東側にブランドショップが点在していた従前の状況に対し、次第に西側へショップが展開していったということですね。
浅子:「地」としてのアイコン建築が建ちならびはじめたのはそれほど昔の話ではなく、案外最近のことなのです。ぼくはその時代のことを「ミレニアム」と呼んでいるのですが、1990年代後半から2000年代初頭のわずか数年の間に建築家とブランドのコラボレーションによるアイコニックなビルやショップがそれこそ世界中で雨後の筍のようにつぎつぎに生まれました。青木淳とルイ・ヴィトンの関係が始まるのもまさにこの時です。
さらに表参道について言えば、2003年に解体されるまでは、なんといっても同潤会青山アパートが圧倒的な場の空気をつくっていましたよね。敷地の内部には通行人も歩ける未舗装の部分が残っていて、裏通りも含めて、住宅や商店が混じりあうような、そんな土っぽさが残る独特の雰囲気がありました。
日埜:現在は建て替えられてしまいましたが、1970年代につくられた丹下健三の《ハナエ・モリビル》の全面に張られたミラーガラスのファサードが、当時は圧倒的に新鮮に見えた。いわばアイコン的建築として受け止められました。
先ほども申し上げたように海外からの資本が原宿に入ってくる状況は1990年代に生まれました。単に東京をマーケットとしているわけでなく、アジアの旗艦店という位置付けがありました。《アップル》の場合にどういうスキームがあれを成立させているかはわかりませんが、容積を使い切ることをばっさり切り捨てているあの大胆さからして、明確な事業スキームと、撤退までの時間軸を視野に入れた企画なのでしょう。

日埜直彦氏
■看板としての建築
日埜:表参道の《アップル》にかぎらず、アップルストア一般についての僕の基本的な理解は、アップル社が最重要視しているのは、商品を売ることそのものではなく企業イメージを打ち出すことにある、ということです。その点では銀座の《ソニービル》がかつて担った役割に似ている。アップル製品が作っている世界観、そして企業イメージをプレゼンテーションする「看板」建築ではないでしょうか。言ってみれば、ヴェンチューリがいうところのダック建築ですよね。
市川:たしかにアップルストアにはアップル社の「看板」としての機能が期待されていますね。アップルストアの歴史をおさらいしておくと、一号店は2001年にバージニア州のショッピングセンター内につくられていて、その頃からすでに「体験を売ること」や「アップルコミュニティへの招待」という名目を掲げています。販売だけでなく「アップルを買う」という特別なイメージや体験を提供するモデル空間だと捉えられてきたわけです。ただしインテリアの様子は少し違っていて、初期は什器が曲線のものであったり、ジョン・レノンとオノ・ヨーコの写真が象徴的に飾られていたりする。
アップルストアの「看板」的性格ということで言うと、ニューヨーク五番街の店舗や上海の店舗が際立っています。この二店舗に共通するのは、客が滞在する空間がすべて地下フロアにまとめられていて、地上にはガラスの壁と屋根でつくられた透明なエントランス空間しかない点です。外から見ると、中空の透明な物体、そしてそこに吊り下げられたアップルアイコンしかない。空間を内包する建築でありながら、そこにアップルストアがあることを示す文字どおり「看板」となっています。表参道の《アップル》の構成もこれらと基本的には同様ですね。ただし、地上フロアでも商品が陳列されているので、五番街や上海に比べると「看板」としては不純と言えますが。
日埜:五番街や上海のアップルストアの場合、都市的パブリックスペースに隣接しているというシチュエーションにあるため、地上にガラスのキューブや円筒のようなシンプルなヴォリュームだけ突き出してエントランスとし、そこから地階に降りさせるという構成が効果的です。ガラスのエントランスが大きな引きをとって印象的に見えるし、外から店内を覗き込む見え方も特徴的です。しかし表参道の《アップル》では、既存のパブリックスペースはなくて、つまり表参道に面するだけで、両サイドのスペースも狭い。パブリックスペースのなかにある彫刻というよりは、むしろ温室みたいに見える。

表参道沿道から店舗西側をみる。

表参道沿道から店舗東側をみる。
市川:そもそも、アップルストアの「地下に掘る」というアイデアはどのような思想から生まれているのでしょうか。
浅子:猥雑なものを外に見せずに済む、ということでしょうね。つまり「ミニマル」の思想です。五番街のアップルストアはその最たる例でしょうが、さらに限界まで推し進めたのがイスタンブールの《アップルストアZorluセンター》でしょう。
吉本:設計はノーマン・フォスターですね。外観はほとんどMac miniのようです。
浅子:昨年の末、フォスターの事務所でアップルストアやアップル新本社ビルにも関わられた鶴巻崇さんの講演を聞く機会がありました。「ハイテックとミニマルの融合」について話されていましたが、このキーワードはアップルのプロダクトとアップルストアの設計思想に通底するものです。アップルの本社ビルはご存知のように、中央に中庭を持った巨大なドーナツ型のオフィスビルですが、カーブしたガラスはサッシレスで徹底的にミニマルに納めながら、自然換気を行うために、庇の裏に風速を制御する技術も導入しています。
鶴巻さんの講演で印象的だったのが、イスタンブールのアップルストアが完成した時点でフォスターの元でやることはなくなったと思った、というエピソードです。この発言はとても象徴的で、ある意味でミニマルのデザインの限界をよくあらわしている。アップルのミニマルなデザインは洗練さを競うものですから、ある程度のところまで行き着いてしまえば、その後は細かな完成度だけが焦点になってしまう。だからこそ、作る側も見る側も退屈に感じるのではないでしょうか。僕としても、ニューヨーク五番街とイスタンブールのアップルストアが臨界点に達した作品だと感じており、このふたつと比べると表参道の《アップル》はいささか拍子抜けでした。たとえばすべてガラス「だけ」でできたファサードは手法としてわかりやすいですが、大判のガラスを5枚もはさみこんでいるから小口がほとんど黒ずんで見えてしまう。東京国際フォーラムの中にも渡辺邦夫によるガラスだけでできた庇がありますが、何枚もガラスとアクリルを重ねた結果、濃い緑色になっていているので透明感は皆無です。どちらも、当初は透明なものを作ろうと思っていたからこそ、余計なものを取り除き、ガラスだけでデザインしたのだと思うのですが、その結果、「ガラスだけでできている」という事実だけが重要視されてしまい、重く不透明なものができてしまっている。意固地になったせいで本末転倒しており、デザインとしては未熟だと感じました。
鶴巻さんは、その後ロンドンのトーマス・ヘザウィック事務所に移ったそうです。ヘザウィックはプロダクトデザイナーとして知られていますが、現在は大型プロジェクトがいくつも動いており、建築設計事務所化しつつあるそうです。この状況はアップルストアの今後を表しているように思います。
日埜:半年ほど前に香港でヘザウィックの大規模な展覧会を見たのですが、彼がやっているのは「プロダクト」であって建築ではないなと感じました。面白いのは間違いないけど、たとえばプランニングの問題、空間的な組み立て、周囲との多面的な関係の建築としての対応、そういったことはテーマになっていない。
イスタンブールのアップルストア以降に行き場がなくなるのだとすれば、それはやはり、アップルストアが建築というよりは、「看板」というプロダクトとしてつくられているからでしょう。アップルからすれば、アップルストアもまた「自社のデザインを前面に打ち出すショールーム」というプロダクトでしかない。商品もアップルストアも、厚手のアルミを梨地で使い、ガラスの透明さと組み合わせ、そのディティールはシンプルだけど念入りに細工する、同じスタイルで統一されている。アップルのプロダクトとアップルストアとがデザイン的にがっちり組合って一貫性があるけど、どこかしんどいといえばしんどい。
結局この方向でやるかぎり、周囲の街との応答関係や、そこで起こりうる多様な出来事の背景としての建築みたいな多面的な建築の問題はあっさり捨象されます。こうした複雑な問題こそ、建築の豊かさのルーツであるはずですが、それらを断ち切って「看板」に還元している。
ただ、そもそもアップルストアに限らず、アイコン建築というのはそういうものだとも言えます。ヘルツォーク&ド・ムーロンの《プラダブティック青山店》や《ミュウミュウ青山店》などにも、そういう側面は多かれ少なかれあります。それらの建築としての質を十把一絡げに扱うわけにはいかないけど、結局アイコン建築がまさにアイコンである限り、建築が多かれ少なかれ「看板」に還元される。
浅子:《ミュウミュウ》の設計者のヘルツォーク&ド・ムーロンは表参道について「ここにはヨーロッパならあって当然の都市の個性が入り込む余地などまるでない」などと書いていますね(『新建築』2015年5月号)。大変ひどい話で、その土地のコンテクストを読み取る能力がないことを棚上げにして、閉じた箱をつくることを正当化している。悪いのはすべて街のせいだと言わんばかりで、建築家としては極めて問題のある発言ですが、次号の月評で誰も反論しなかったことにも大変失望しました。ただ同じ設計者でも《プラダブティック》はいいと思います。建物を塔状にして建築面積を抑えることでオープンスペースを設けているからです。あと、表参道の商業建築のなかで、周辺環境との関係でいいと思うのはMVRDVによる《Gyre》ですね。裏原宿のぐねぐねした通りを立体的に積むという発想から形態が導かれています。屋上に庭をつくった《東急プラザ》も同様によくできている。
これらのように、アイコンとしての要求に応じつつ、限られた条件のなかでオープンスペースを設けているか否かという点は、日埜さんがおっしゃる看板と建築の差を見極めるポイントのひとつになると思います。
■「消費している私を確認する私」の空間
市川:《アップル》をあくまでも建築、あるいは商空間として見ようとしたとき、お二方はどのあたりに注目されますか?
日埜:階段ですかね。上海、浦東のアップルストアのガラスの階段を見たときは驚きがありました。ガラスの円筒部から地階に降りていくようになっているのですが、地上部から廻りながら降りて行くにつれ、地下の店内がゆっくり展開して見えてくるシークエンスが見事でした。表参道店でも同様の階段が作られていて、アップルストアのイメージを決めているところがあると思います。すこしボッテリした寸法ですけど、よく計算されていると思います。
浅子:しかしそれなら似たようなデザインは昔からありますよ。エヴァ・ジクリナというロンドンの女性建築家が、いまのアップルストアと同じようなガラスの階段をいくつもつくっています。踏面が透明で吊材を細い金属にしているところも、中心に階段を持ってきて、それをインテリアの焦点にするというプランも一緒なので、僕にはその焼き直しにしか見えない。ただ、確かに寸法は独特で、駅舎のような公共空間の寸法が入っているように思います。
僕は批判はしましたが、やはり透明性が気になります。商業建築を設計する場合、当然ながら入りやすいお店にする必要があるので、外から店内の様子がうかがえるようにしたほうがよいのですが、反対に丸見えだと商品を見る自分も視線にさらされるので抵抗を感じさせてしまうからNGとされています。教科書的な答えとしては「見えつつ・見えない」半透明的な関係性をつくるというものですが、このセオリーからすると、透明度の高い《アップル》はとても入りにくい店舗のはずなのに、そうはなっていませんよね。
複数の要因が考えられますが、インテリア上の工夫としては、テーブルのなかにキャッシャーを隠蔽し、カードのやりとりもiPhoneでできるようにすることで、レジ自体をなくし、何かを買わないといけないというプレッシャーを減らしたことが効いていると思います。ショップというよりも、アミューズメント施設のようなものとして認識しているのでしょうね。
日埜:ブランドショップ全般に言えることではありますが、「そこにいる私が嬉しい」という感覚、その場に自分がいることで特別な高揚感を感じさせる、そういうことにアップルストアは成功しているでしょう。商品を見ているんだけど、どこかでそうしている自分が見られているという意識がそこに重なっている、そういう空間でしょう。いくらかステージのようでもありますが、「消費している私を確認する私」という入れ子的な関係、こう言うとちょっと自意識過剰なようですけどね。ジーニアスバーであったり、たっぷりスペースを取った商品陳列であったり、アップルストア独特の儀礼的な道具立ても効いているように思います。
吉本:まさに建築的な工夫ではありませんが、Tシャツ+ジーンズというラフな格好でフレンドリーに接客する店員の存在も敷居を下げていますね。気さくであると同時にスペシャリストでもある、という設定。
日埜:結局は西海岸的なスタイルですよね。気取らないドレスダウンなんだけど、それがそのままスタイルになっている。ある種「オープンマインド」的という点では、イームズの《ケーススタディハウス》あたりにつながるかもしれない。
浅子:そうなると、《ケーススタディハウス》も建築ではないのか?ということが気になりますが(笑)、それは置いておくとして、アップルは基本的にスティーブ・ジョブズやデザイナーのジョナサン・アイブなどのトップの意向があらゆるプロダクトに浸透しており、それがアップルストアのインテリアにも貫徹されていることが重要でしょう。そういう意味では昨今のブランドショップのインテリアの制作体制と似ていなくもない。
1990年代までは、ファッションデザイナーの意向にインテリアデザイナーが応じる体制がある程度定着していました。倉俣史朗やデヴィッド・チッパーフィールドの仕事がその例です。しかしこの20年ほどで、ファッションデザイナーのうちの一部は、自身の役職をクリエイティブ・ディレクターと名乗り、洋服に加え、広告やウェブサイト、さらにインテリアデザインなどを一身に引き受けるようになってきました。そこでは、ある種の「万能人」的なキャラクターが求められる。インテリアの代表的な例として、アップルストアの隣にあるエディ・スリマンの《サンローラン表参道店》がありますね。一連のアップルストアについても、アイブの意向によってプロダクトの一貫性が保たれているという点で、クリエイティブ・ディレクター型の典型例ともいえるかもしれません。
日埜:アップルがつくっているマスプロダクト、それとまったく同じプロダクトデザイナーの目でアップルストアが作られているということですね。店内のディスプレイは、同じ型のMacBookやiPhoneが数十台ずつ、季節感に関係なく置かれ、客たちも天井高があるフロアのなかの群衆として点景となり、「看板」の一部をなしているかのように見える。つまりアップルストアのプログラムは、物販というよりも「消費行動」であって、それ以上の多様な出来事は起こらない。そして結局その全体がきれいに「アップルストアというパッケージ」のなかに収まってしまう。だから、アップルストアにあるのはアップル製品のイメージであって、商品そのものではない。変なことを言うようですが、ある日とつぜんアップルが倒産して《アップル》で別のプログラムが生まれたりしたら面白いと思いません? たとえばこのガラス張りの空間で卓球とかしていたらかっこいいかもしれない(笑)。
市川:客と店員を含めた「アップルコミュニティ」を対外的に展示するという点からすれば、表参道の《アップル》は五番街や上海よりも純粋な「看板」だと言えますね。

浅子佳英氏
■ミニマルの隘路
浅子:看板か建築かと言っていても答えはないので、話を進めると、そもそも「ミニマル」が1990年代に使い古されたネタであって、それを突き詰めてもゴールはないというのが僕の考えです。コールハースは、消費することの後ろめたさを隠す役割をミニマルが果たしていると批判的に指摘しています(「ジャンクスペース」『S,M,L,XL+ : 現代都市をめぐるエッセイ』所収)。僕もその通りだと思う。そしてこれはアップルのプロダクト全般に通じることではないでしょうか。「数多ある他のマシンよりも無駄がなくシンプルで完成度も高く、長く使えますよ」とメッセージを発している一方で、実際には一年に一回のサイクルでモデルチェンジを行なうんだから。
日埜:どうかな。ただコンシューマーグッズとしてのプロダクトをつくっているだけにも思えます。むしろアップルの思想のなかにはもう少し真面目な意味もあるはずです。僕がアップル製品を最初に使ったのは25年ほど前でしたが、モノとしての完成度は他のコンピューターとは比較にならなかった。当時はコンピューターにデザインなんか事実上存在しなかったわけですけど、そのなかでプロダクト・デザインとしてのコンピューターを意地でもずっと追求してきたのは認めざるを得ない。そうしたブランドイメージに対する一貫する哲学があったと思います。
浅子:ただ、一年でモデルチェンジする点にはひっかかりますね。
日埜:モデルチェンジを繰返しているとはいえ、遠くから見ればけっこう同一性があるように見えません?
浅子:だからこそ最新版が一番良く見えてしまうわけで、そこに大きな問題がある。アップルストアのようなミニマルな白い空間の建物はとてもシンプルで、ギリギリまで無駄なものを抑えて「究極の答え」を限界まで追求していくようなデザインだと言える。しかし次の年には結局最新のものに更新される。それ以前のデザインは「旧バージョン」として簡単に取って代わられるわけです。そのようなやり方は、すでに今の時代に合っていないし、限界があるでしょう。
日埜:それはアパレルブランドのブティック全般にも言えることだと思いますが。
浅子:たとえば冒頭で少し話しに出た《イザベルマラン表参道店》には、そのような心配は随分と少なくなっていると思いますよ。イザベルマランの店舗は世界各地にありますが、思想としては一貫しつつも、それぞれ異なるデザインになっています。だからこそ時間の経った店舗が「旧バージョン」として古びる問題はかなり薄まっている。
日埜:そうでしょうか? 昔のお店には今年の新しいコレクションが置きにくい、ということが多かれ少なかれ生じているような気がするのですが。ファッションブランドというのは一般に消費の対象であって、インテリア・デザインがどうなっていようと、結局はつねに新しいことを追求し続けなければならないし、許容出来る範囲と言っても程度問題では。
浅子:大局的に見ればそうかもしれません。たしかに、どのブランドも大なり小なりそのような問題は抱えてはいます。けれど事実として、イザベルマランのように場所によってデザインを変えるなど、今までとは違うやり方を考えているブランドショップが最近増えつつあります。Aesopなんかもそうですね。そのような状況をふまえると、アップルストアのミニマルな方向性はあまり褒められたものではないように思うのです。
また、東日本大震災からわずか数年しか経っていないこの状況の中で、アップルストアのような維持コストのかかるつくり方についても首を傾げたくなります。全面的に空調を使わないと維持できない商空間をつくっているのに「シンプルで無駄を排除したデザインです」と言われても、いまいち説得力がないのではないか。
とはいえ批判し過ぎてもしょうがないので付け加えると、ノーマン・フォスターが最近デザインしたサンフランシスコのアップルストアはけっこう良いと思います。スライド式の巨大なドアを正面に導入していて、これによって建築を街につなげようとしている。実際に開閉が可能なので少なくとも中間期は空調のみに頼ることにはならないでしょうし。
日埜:街への展開ですね。しかし、これですら僕には建築ではないように見えます。テクニカルに言っても、飛行機のハンガーみたいなものでしょう。本来建築が持ちうる多様なありかたを切り捨てて、あらかじめ出せる答えを限定してしまっていて、どこか貧しいように思います。
浅子:それはよく分かるのですが、少なくとも開口が開かない他のアップルストアよりはまともだと言えませんか。表参道の《アップル》の場合、引きがとりづらい敷地なので、ガラス張りのファサードをつくっても圧迫感が増しただけになっています。裏やサイドに中途半端なスペースがありますが、全く使えない。アップルほどのブランド力があれば表参道に建てる必要なんかなくて、もっと引きのとれる敷地に変えるという思いきった選択をしてもよかったでしょう。しかし、改めて考えてみると、ローカルアーキテクトの光井純氏による、少し前までカルチェの入っていたザ ジュエルズ オブアオヤマや、こちらはシーザー・ペリ&アソシエーツジャパン名義での仕事ですが、大阪の国立国際美術館も地下に埋めたタイプの建物でしたね。このふたつの建物も街との関係という意味ではあまり上手くいっているようには思えないので、もしかするとアップルではなく光井純氏の問題なのかもしれません。
市川:ミニマルというお話が出ましたが、透明性や平滑性、目地をできるかぎり少なく目立たなくさせる、つまるところ物質を非物質的なところまで落としこむ、という点において、アップルストアの美学はモダニズムの延長線上、その最果てにあると言えますよね。世界中の都市で基本的には同じようにつくるというインターナショナル性もそうです。
浅子:モダニズムがそもそもミニマル的ですからね。ミースの建築も一面ではそうであって。
吉本:建築的な規範のもとでみると、そのような見方がオーソドックスですよね。ミニマリズムという近代的な価値観の延長線上に、アップルのプロダクトを位置づけることはもちろんできると思います。逆に、アップルストアの建築的ではない部分に着目すると新たな糸口が掴めそうな気もします。近代から続く時間軸をいったん解除して、現代的な問題としてミニマルなものを捉えるとどうなるでしょうか。
日埜:かつてミニマルといえば、カルバン・クラインのショップみたいなものを指していました。そこではまず素材自体がおそろしく高価で、石なら分厚くソリッドのまま、金物も入念な仕上げの無垢材削り出し。これに対してアップルストアの場合はそういう意味ではゴージャスではない。一般に流通するガラス、アルミ、コンクリートなどを用いつつ、それを大胆にブラッシュアップするという方向で、むしろこれ見よがしにゴージャスな素材は意識的に避けているかもしれない。商品における素材の使い方とも重ねられていて、やはり発想がプロダクト的です。
ちなみに僕が《アップル》を最初に見たとき、たまたま雨上がりでエントランスのガラスの庇の下をスタッフが拭いていたんですね。それでああこれはプロダクトだなと感じたんです。水が切れないから裏側に水が廻る。放っておけば汚れもたまるでしょう。鼻先にFB一本入れて横に流しても良さそうだけど、でもクリアカットのガラス小口を見せるのがアップル製品のデザインでしょう。もちろんマンパワーでカバーしても良いと言えば良いんだけど、考え方として建築ではないよなと思ったわけです。
浅子:カルバン・クラインの設計者であるジョン・ポーソンは「minimal」という本まで出版していおり、確かにかつてはカルバン・クラインやジル・サンダーがミニマルの典型例でした。
まあただ水切りについていえば、現在は気にしない建築家もたくさんいる気がしますけどね(笑)。

エントランスのガラスの庇

市川紘司氏
■ゲーリー、あるいは「コンビニ的」な空間との距離
市川:あるレイヤーのなかで《アップル》と対比的に考えられる建築を考えてみたときに、フランク・ゲーリーの建築があるかなと思いました。いずれもアイコン建築というテーブルに載り、西海岸的で、ハイテクという点も似ている。ただ、一方はあくまでも建築として評価され、他方はプロダクトであると評価される。
異なる点としてはひとつ、目地の扱いかたがあるのかなと思います。SANAAのお二人と藤本壮介さんは、エレメントの構成が強調されるモダニズムの目地の出し方に対し、ゲーリーの建築はむしろ目地を徹底的に出すことで目地を消してしまったところが興味深い、というコメントをしています(『GA JAPAN』136号)。アップルストアが究極的に目指すのは目地のない完璧に透明な空間でしょう。しかし建築はスケールが大きいからこそ、ものとものの接合する箇所がプロダクトよりも目につきます。目地が出ることを前提にそれをよく検討してデザイン的に消化するのか、それとも目地それ自体をなかったことにしようとデザインするのか。その違いが両者の評価のされかたに関わっているように思います。
浅子:ゲーリーの《ビルバオ・グッゲンハイム美術館》はその特異な形態のせいでハリボテだと言われがちですが、僕は少し別の見方をするべきだと常々考えています。語義的には中身と外身が一致していないものを「ハリボテ」と言いますが、《ビルバオ》のモチーフである「魚」の複雑な形態は内部の展示室にもそのまま出てきていますよね。反対に、展示室の四角いヴォリュームがそのまま外形に表れている部分もあったりする。だから僕の見立てとしては、尻尾に当たる部分を除けば、《ビルバオ》は内部と外部は解離しているわけではないのでハリボテではない。
日埜:僕は《ビルバオ》はやはりハリボテだと思いますが(笑)、それはともかく、極限まで形態操作されたゲーリーの建築とミニマルなアップルストアの間にはたしかに対立軸を引けます。でも面白いことにゲーリーのデザインはあのスケールだとアリだけれど、どうも小さな商空間だと上手くいかなかったりする。
浅子:ゲーリーはニューヨークなどでいくつかインテリアを手がけていますが、おっしゃるとおり、あまり良くないですね。
日埜:ゲーリーの作る建築の持っている独特のスケールが、商品を陳列するような商空間には合わないんですよね。美術館と商業店舗では、置かれるモノの大きさも見せ方もぜんぜん違う。どっちが偉いというわけでもなく、違う種類の要求なんでしょう。その要求にゲーリーの建築のアプローチではうまく応えられない。アップルストアの場合は、単に商業店舗の見せ方というのともまた違う独特のスケールがあります。通路幅でも什器でもちょっとずつ大きくて、商品が空間の中にアイコンのように見える。そしてそのアイコンの間を充填するのがアップルのブランドイメージっていう感じです。
もう一つ補助線入れてみるなら、アップルストアとはつまるところ「高級なコンビニ」だ、とも言えるでしょう。コンビニが店舗ごとに独自の個性を持ったりしないように、アップルストアにはある確立されたフォーマットがあり、そのフォーマットに浸りに顧客は来店する。必ずしも買いにきてるわけじゃないですよね。商品の間をふらふら歩いてひやかしているだけでアップルストアとしてもぜんぜんかまわないはずです。そうしてアップルのデザインイメージが伝わるんですから。
家電量販店の中でもアップルのコーナーはちょっとしつらえが変わっていますね。白くて見通しよく広々している。売り上げにしのぎを削るフロアの中でいろいろ頑張ってるんだけど、でもあれはアップルストアと同じにはなりえない。アップルストアには先ほど言った「そこにいる私が嬉しい」みたいな変な高揚感があるけど、家電量販店のコーナーにそれはない。でもアップルにとって、その高揚感こそがブランドとして欠かせないはずです。
浅子:そうですね。ただ、これはブランドブティックも同じ傾向なのですが、利率を考えても旗艦店で商売したほうが得ということもあって量販店への出店は控えているらしい。
「コンビニ的」という点から言うと、アップルのインテリアはまさにそのものです。手前のファサードがガラスになっていて、家具をグリッド状に等間隔に並べる配置は普通のショップではまずやりません。システムとしては管理の合理化を徹底するためにつくられたコンビニの商品棚にアップルストアは似ています。コンビニでは一週間ごとに商品の大きさに合わせて棚の高さや配置を変えたりしているのですが、その作業が一律で行なえるように、カセットをすべて同一規格にしていますよね。そのようなコンテンツの入れ替えに対応している点もアップルストアは同じです。
市川:バブル前後に伊東豊雄さんがコンビニをよく論じていました。都市のいたるところにコンビニがある(「サラン・ラップ・シティの建築風景」『透層する建築』)。それは建築的に肯定するわけにはいかないものの、しかしそういう状況に対して無視を決めこむのではなく、むしろ「コンビニが無数にある」という「空気」や「感じ」を背負わなければ新しい建築はつくれない。そのような主旨であったと思います。《せんだいメディアテーク》のときにも「情報のコンビニ」をキーワードにしていましたね。
プロダクトや高級コンビニではなかろうかという日埜さんの評価もよく分かるのですが、とはいえこの小委員会の特集で取り上げようと思ったのは、だからといって建築の議論のテーブルに載せられていないのもどうかなと思ったからでした。現実問題として、アップルストアに関する取材というのはアップル側の許可をとることなどが非常にむずかしくて(ディズニーのようなものです)、なかなか建築ジャーナリズムのなかで語られてきてない状況です。ただ一方ではそれが建築として表参道に建ち、世界の人々に少なからず受容されている、という現実がある。であるならば、20世紀末のコンビニのように、わずかばかりでも議論の片隅に置かれてしかるべきではないかと。
浅子:たしかにコンビニを排除するのではなく、現代の人々の感性に一致していると見たほうが、話の通りは良いですね。でもそれだと「アップルストアはコンビニのデカい版である」という結論になってしまいますが。
あらためてアップルという企業がすごいと思うのは、同じものをつくり続けているように見えて、iTunesにしろiPhoneにしろ、プロダクトを支える根底のプラットフォームの部分での大きな書き換えに何度も成功している所です。ネットのインフラや消費形態など、プロダクトを支える裏の部分の仕組みそのものをなんども刷新している。これはもの凄いことです。当然ながら現在のプラットフォームが未来永劫まで続くことはないことは明らかで、iPhoneの次にどういうものが出てくるのかはとても気になります。
吉本:そこに置かれているコンテンツとの関係で空間を捉える視点ですね。コンテンツが変化した時にアップルストアも変わりそうです。
浅子:その可能性もゼロではないでしょう。より根本的な変化がありえますからね。
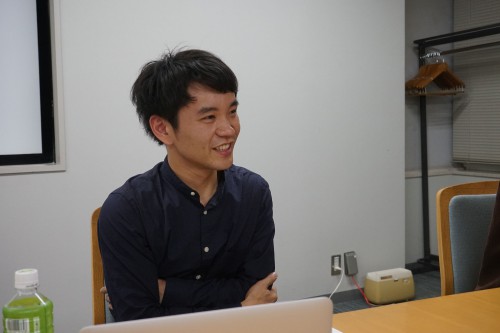
吉本憲生氏
■「良識的」な建築の思考と、建築・都市を語るための言葉
日埜:すこしこの話を振り返ると、市川さんが冒頭で提起されたのは、実際に表参道の街並みを「地」とする《アップル》が「図」として特別なものにも見えるのではないかということでした。それに対して僕が思うのは、《アップル》は周囲の町並みのコンテクストとは無関係に、ただひたすらアップルという企業の文脈、必然性のもと、プロダクト=看板としてアップルストアをつくっているだけではないかということです。だからむしろ考えどころは、アップルストアそのものではなく、むしろ見る側にあるんじゃないか。「アイコン建築がたくさんある街並み」という表参道に対して漠然と抱くイメージがまずあって、そのフィルターを通して《アップル》を見てしまうから特別なものに見えるし、反アイコンにさえ見えてしまう。
たしかに《アップル》のデザインには、そのような見方を誘発するような、意表をつくようなところがある。それは事実でしょう。そして、だからこそ見る側のそのバイアスがより強く浮き彫りになるのではないでしょうか。たとえば僕の場合は「これは建築ではないよね」とか「ちょっと単純過ぎてしんどいな」と見えるわけですが、しかし同じものが「奇をてらわないスタイル」であったり「正直で素直なデザイン」として目に映ることもあるわけでしょう。
市川:その通りだと思います。そのうえで私が興味を引かれたのは、建築を専門とする人間と一般の人たちでそのバイアスがけっこう大幅に異なるのではないかという点です。
日埜:さきほど伊東豊雄さんの「サランラップシティの建築風景」の話が出てきましたが、まさにいわば「飼いならされた消費者」となった我々は、どう建築に反応し、期待しているのかということになるわけですね。例えば一般の人はあの三面ガラスの巨大な箱という建物の姿に対して素直に驚くわけでしょう。それを突き詰めて言えば、「量」に対する単純な驚きですよね。巨大なガラス面、構造などの視線を邪魔するものがなく、ただひたすらガラス。わかりやすく即物的にスゴい。他方で私たちは、建築にもう少し複雑なものを求めている。都市の中で対話的な街並みの関係を期待し、都市生活の一部としての消費行動の器として商業建築を想定している。それはやたらと理想論を並べているわけでなく、実際都市の中にそういうものはあると思っている。
たとえば先ほど名前が出たフランク・ゲーリーにしても、彼がやっている仕事の最良の部分はそういうところにあるでしょう。そしてそれを支えている設計や施工は現在のカッティング・エッジのテクノロジーに支えられていて、いまだからこそできることをぎりぎりまで突き詰めた結果として彼の建築は生み出されている。専門家としてそういう可能性を見た上で、アップルストアを見てこんなことに虚を衝かれていてよいのだろうかと思ってしまうわけです。
私たちが都市の中での消費行動をどのようにイメージしたらよいかということが、戯画的にアップルストアには表れています。でもそれは専門家と一般の方々のあいだにギャップがあるからそれを反省するっていう単純なことではないはずでしょう。もちろん、アップルストアで起こっていることを建築的にちゃんと考えてみることにはもちろん意義があるはずだし、そこで一つの手がかりとして一般の人の反応とのギャップを考えるのはアリだとは思いますが。
市川:個人的には、建築を丁寧につくろうとする「良識的な建築家」と、建築をイメージやマスプロダクトとして捉える傾向のあいだにある乖離がずっと気になっています。これはしばらく中国にいたことが大きいのかもしれませんが。
吉本:こうしてアップルストアについて考えてみると、建築的な発想に基づくものではないからこそ、「やられたな」と虚を衝かれる状況が生まれているといえそうです。一方、同じ理由で、プランや空間の問題として語ることがなかなかむずかしいことに気づきます。アップルストアそのものを、「良識的」な建築の文脈に引き寄せて考えるかぎり、議論を展開させていくための新しい言葉を見つけ出すのは難しい。しかし、このことを翻って考えてみると、建築的な思考をとりまく制約など、現在の建築が置かれている状況が逆説的に浮かび上がってきそうです。このことについてはいかがでしょうか。
日埜:「良識的な建築家」と言っているのは、例えば良識的な人間像を前提として建築をつくる人のことじゃないでしょうかね。人間の多面的な振る舞いがあり、そしてそれが相互作用する社会からの複雑な要求がある。そんな多様な関係の中にある器として建築を作るということがそこでの前提です。
しかし実際は、人間はそんなに「良識的」な存在でなく、むしろもっと野蛮かつ家畜化した存在なのかもしれない。「飼いならされた消費者」というのはかなり強い言葉ですけど、実態としてそういう状況はある。アップルストアだけでなく、数多くのアイコン建築が建ち並ぶ表参道はいわば動物園のようなもので、ヒューマニスティックな良識がどこまで意味あるものなのか一瞬不安になるのも当然かもしれません。それでもなお、建築に出来ることはもっと多様だとやはり確認しておきたいわけです。
浅子:うーん、、ちょっと話がねじれているような気がします。そもそも日埜さんの立場としては、アップルストアは「看板」であり建築ではないということでしたよね。今日、僕は否定的であれ《アップル》について色々と指摘してきたのは、やはりこれを「看板」と言って切り捨てないで、ひとつの建築として語ったほうが良いのではないかというぎりぎりの抵抗の意識だったのですが。
日埜:確かにややこしい話になっていますが、簡単に単純化したくないところです。「良識的な建築」についての矜持を建築の専門家が持つ一方で、一般の人からすると「看板」でも構わないという状況があり、現実にも「看板」で溢れた都市がある。その状況下では、良識的な建築家が「アップルストアは建築ではない」といえば済む問題では確かにすでに無い。しかしそこで考えるべきは、現代の都市に対するその良識を非現実的と簡単に引っ込めるのではなく、それを再び鍛え直すことでしょう。そこで僕は建築の複合性や多様性を簡単に非現実的とは言いたくない。
そういう僕の立場と浅子さんのおっしゃる立場は拮抗しているのではなく、現代の都市をめぐる問題に対するアプローチとして、表から向かっていくのか裏から攻めていくのか、という違いじゃないかと思いますよ。
浅子:とはいえ、アップルストアなんて所産看板だよね、ということで納得してしまう読者が少なからず生まれそうでうんざりするのですが、、。そもそも僕にはアップルストアに対して語る言葉がないということよりも、商業建築全般に対する言葉の少なさが根本的な問題としてあるように思えます。
ポジティブに見れば、商業建築やインテリアデザインは、大量の人々の欲望をどうやってコントロールするかという実はかなり複雑で困難なことを当たり前のようにやっているわけです。ただ、インテリアのデザイナーはそのことを積極的に語ろうとはしません。魔法の種明かしをするようなものですから。そんなこともあって商業建築は「無批判に人々の欲望に応じるままにつくられたアイコン」であるとしばしば断じられるわけですが、そうやって批判する建築家もなにか言ったような気になっているだけで、そのなかで実際に起きている中身については語ることはなく、なぜかブラックボックスのままで良いことになっています。
当然ですが、実際にはその中にも無数のルールがあります。たとえば百貨店のエスカレーターまわりの動線は、他の店舗に入る機会をつくるために、あえてフロアのなかをぐるりと歩かせるように計画されている。分かりやすい話としては、見通しを悪くさせるためにあえてカーブした動線が使われています。すぐに奥まで見通せてしまうと、それ以上先に行きたいと欲望させることが難しくなるからです。ただし客がひとつのショップを眺める時間はだいたい3〜5秒くらいだから、その数秒でいかに人々の欲望を喚起するかが勝負になります。商業建築をやっている一部の人達はそのための手練手管をたくさんもっているんですよね。
地方都市でのまちづくりやコミュニティの建築が流行していますが、都市部の再開発などは昨今でも俄然進められているわけで、そうしたブラックボックスのなかで行なわれていることをきちんと読み解いていったほうが、現代の都市の問題を考えるときに豊かな知見を与えてくれるものになると思い、この数年はインテリアデザインの研究を進めています。
もうひとつ、西海岸という話が途中にでましたが、そもそも西海岸の文化には自分たちの世界は自分たちでつくろうというDIY的な精神があったはずです。IBMという巨大企業に対抗心を燃やし、ガレージでパーソナルコンピューターを自らの手でつくって販売までしたかつてのアップルは、まさにそういう意味でもとても西海岸的だった。それが、いつの間にかミニマルという洗練の呪縛に囚われてしまい、かつてのDIY的な精神を忘れてしまっているのではないか。最近はプロダクトもその方向を向いていて、MacBook Airはハードディスクもメモリもカスタマイズすることができません。表参道のアップルストアはそういう意味でもとても象徴的です。やはり向かうべく先は洗練ではなく、新しい世界を自分たちでつくるのだというDIY的で野蛮な世界ではないでしょうか。
日埜:商業抜きの公共なんてあるわけがない、ということへの認知が薄いのではないかという浅子さんのお話はおっしゃるとおりですね。都市を造る資本の論理という大きなスケールのことから、個人の生活が実際に生産と消費と不可避に関わっているというミクロのスケールまで、我々の社会、公共性は不断に経済と商業を媒介として成り立っている。そこを支えているフィジカルなフレームとしての建築の具体をきちんと語る言葉はまだまだ貧しいのかもしれない。
実際に《アップル》が都市のなかに建っているものとして成立しているわけですし、まあ10年くらいは残っているでしょうから、出来たばかりの新鮮さのなかで見るばかりでなく、ゆっくり構えてみれば自ずとさまざまに見えてくることがあるはずです。とりわけ街との関係ですね。周囲のオープンスペースがどうなるか、あるいは街全体に対してどういう関係を持ってくるか、などいろいろな視点から考えていくことができるでしょう。時間が経ってデザインが陳腐化するなら、そこにプロダクトデザインの寿命と建築デザインの寿命の考え方の違いをみる良いサンプルになるかもしれない。あるいはひょっとするといつかあそこが本当に卓球場になって、プロダクトデザインの皮を被ってもやっぱり建築は建築だなぁと腑に落ちるのかもしれませんよ。


最近のコメント