2011年、東日本大震災と福島原発災害を体験し、その復興過程に関わりながら、そしてまた2015年9月の安全保障法制・関連法案の政府・与党の強行突破の姿に接しながら、あらためて、わが国における“民主主義”の未成熟に思い至ったのだった。大震災とりわけ原発事故が発生した直後の政府の情報発信の不透明性がその後の復興過程に大きな影響を与えた。わが国では現在なお、政府や行政は透明性の高い情報発信をしようとする姿勢すら欠けている。また災害復興の過程において被災地各地で復興計画策定のための委員会や仮設住宅など避難者支援の活動が進められてきた。そこでは、もちろん、さまざまな意見が飛び交った。しかし、「合意形成」のプロセスは困難をきわめた。行政は、行政提案に理解を得ること、支持してくれる過程を「合意形成」の過程と認識している場面が余りにも目立った。原発災害は、初動期の情報、放射線汚染の安全基準、除染、避難区域の地域指定などの結果、賠償問題や避難生活支援さらには復興計画などに様々な対立や分断を生じさせた。色々な意見が存在していることを認め合うこと、一人一人の人権を重視すること、それこそが民主主義の原点である。それらをあまりにも軽視するわが国の体質を眺めた時に、民主主義の未成熟あるいは空洞化を懸念せざるを得ない。
2014年、政府は「国家戦略特別区域法」を成立させた。東京都も、東京を世界でもっともビジネスしやすい都市にするというメッセージを発している。その東京も、近未来は高齢化が急速に進むことが予想されている。殺伐とした事件も続発する中で、改めて都市のあり方について、生活者や地域社会(コミュニティ)が主人公として未来を描く民主主義のあり方が問われている。
1960年代、1970年代、わが国の高度経済成長政策真っ只中で建築・都市計画を学び、建築や都市計画の道に進んだ専門家にとって、今日のわが国が歩むプロセスをどう認識し、発言していくかは大きな課題になっているはずである。
1960年代半ば、大学で建築学を学び始めた頃、『伽藍が白かったとき』をはじめル・コルビュジュの書籍を読みあさった。そして彼の影響を強く受けた坂倉準三、前川國男、丹下健三、吉阪隆正各氏の建築を見学することが多かった。ちょうどその頃、神田の古本屋で見つけたサンドバーグ『シカゴ詩集』の最初の詩「シカゴ」に衝撃を受けた。『シカゴ詩集』は都市をどうとらえるかを学ぶ上でも刺激的であった。同じ頃に接した書籍でありながら、正直に言えば、その時にはそれらの関係性などについてほとんど考えることもなかった。
それからおよそ半世紀経ち、激動するわが国の姿、そして都市の変貌ぶり、そして2011年の東日本大震災における復興過程の問題性に接しながら、あらためてサンドバーグを読もうと思った。『シカゴ詩集』は1916年発刊で2016年はちょうど発刊100年だったからでもある。ル・コルビュジェ『伽藍が白かったとき』は1937年発刊である。そして、両書とも岩波書店から翻訳出版されたのは1957年である(『伽藍が白かったとき』はその後、2007年に岩波文庫として発刊された)。
ル・コルビュジェの『伽藍が白かったとき』や彼の著作は、建築の世界に踏み出そうとしている者にとっては、その「高み」を眺めたり、触れてみたり、場合によっては「住宅は住むための機械である」などに反発してみたり、自らの建築観を築きあげていくときの必読書のような本であった。
ここで主に取り上げるのはサンドバーグ『シカゴ詩集』である。ル・コルビュジェ『伽藍が白かったとき』よりもおよそ20年前に、アメリカの巨大都市の様相を実に冷静に、時には嫌悪感をもって、そして鋭い感受性をもって活写していたのである。
サンドバーグ『シカゴ詩集』

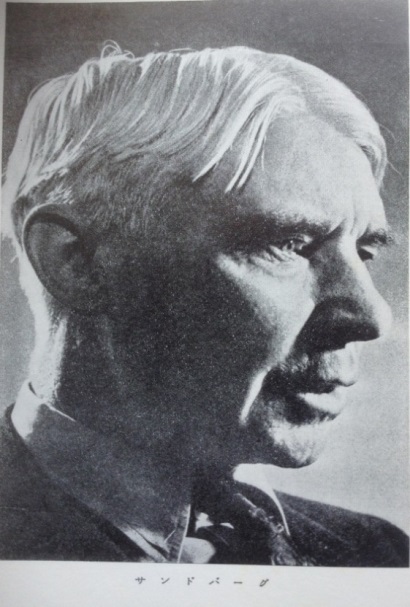
サンドバーグ(1878~1967)の『シカゴ詩集Chicago Poems 』が発刊されたのは、世界を大激震が駆け巡った時代である。訳者の安藤一郎によると、彼自身の大きな人生の転機は1898年の米西戦争であり、一時歩兵部隊に入隊するが、除隊後大学で学び、そこで詩の創作活動を始めた。卒業後はミルウォーキーでジャーナリストとして活動する一方、社会民主党を立ち上げ政治活動にも取り組んだ。1912年ごろにシカゴに移り、雑誌の編集をしながらシカゴで創刊された詩誌『ポエトリー』に投稿していた。同紙に「シカゴ」が掲載されたのは1914年3月号であった。そして1916年4月、『シカゴ詩集』が出版されたのである。
「シカゴという都市は草原の中に、急激に現出したもので、歴史の古い文明の間に徐々として発達した都市とは、全く様相を異にしている。まわりはなお原始性を保つ大草原の自然に取りかこまれ、イリノイ、インディアナ、ウィスコンシン諸州の農夫たちは、工場の煤煙が見えるところで、日々耕作に従事している。極度に機械化した生活と、凶暴とも言うべき荒々しい野生の交錯は、一面アメリカ文明の力強い若さでもあろうが、そこにまた、社会の悲劇的矛盾を多く蔵している」(安藤一郎、『シカゴ詩集』、岩波文庫解説、225ページ)。
1914年6月 第一次世界大戦が勃発し(~1918年)、1917年にはロシア革命そして1922年、ソビエト社会主義共和国連邦に繋がっていく。アメリカはこの時期に経済的発展、政治的イニシアティブを実現していくことになったが、国内では、急速な発展を遂げる大都市への労働者や企業などの集積が進んだ。しかし、一方でアル・カポネなどのギャングなどが暗躍するなど、大都市は光と影の際立った姿を示していたのである。このような国内外の情勢の不安定さは、サンドバーグの詩篇には大きく影響している。
『シカゴ詩集』
【シカゴ詩篇】
『シカゴ詩集』第一篇【シカゴ詩篇】の冒頭の詩が「シカゴ」である。
世界のための豚屠殺者、
機具製作者、小麦の積上げ手、
鉄道の賭博師、全国の貨物取扱い人。
がみがみ呶鳴る、ガラガラ声の、喧嘩早い
でっかい肩の都市。お前は不埒だとみんなが言う、おれもそうだと思う、お前のおしろいを塗りたくった女ちがガス灯の下で農村の若者をひっぱたいているのをおれは見たからだ。
それからお前はやくざだとみんなが言う、おれはその通りだと答える、やたらにピストルをぶっ放す兇漢が人を殺し、また自由になって人を殺しに出かけるのをこの目でみたからだ。
それからお前は残酷だとみんなが言う、おれの答えはこうだ-女や子供の顔に無慈悲な飢えのしるしをおれは見た、と。
そしてこう答えてから、このおれの都市を嘲笑する者どもにむき直り、その嘲笑を投げ返して、おれは言うのだ。
ほかにこのように昂然と頭をあげ、活々として粗っぽく強靭で狡猾なことを誇り顔に歌っている都市があったら、さあ見せてくれ、と。
仕事に仕事を重ねるあくせくとした労苦の中で磁力をおびた罵言を飛ばしながら、ここにちっぽけな弱虫の街々を圧倒して、のっぽの、不敵な強力漢が立っているのだ。
舌なめずりしてまさに飛びかかろうとしている犬のように獰猛で、荒野に向って闘いを挑む野蛮人のように抜け目がない。
頭をむきだしにし、
シャベルをふるい、
粉砕し、
計画し、
築き上げ、ぶちこわし、また築き、
煤煙をかぶり、口じゅう埃だらけ、白い歯をむきだして高々と笑い、
おそろしい運命の重荷を背負い、青年が笑うように笑い、
敗けたことを知らない無知な闘士のようにも笑い、
その手首の中には民衆の脈搏、その肋骨の下には民衆の心臓があることを自慢にして笑っている。
笑っている!
半ば裸かで、汗を流して、豚屠殺者、機具製作者、小麦の積上げ手、鉄道の賭博師で、全国の貨物取扱い人であることを誇る「若者」の、がみがみ呶鳴る、ガラガラ声の、喧嘩早い笑い声を高々とひびかせて。
初めて『シカゴ詩集』を読んだときにも、とりわけ強い衝撃を受けたのは、この冒頭の詩「シカゴ」だった。人間性や自然をも蝕む都市のあくなき貪欲さをひるむことなく冷徹に暴き出しながら、一方で「ほかにこのように昂然と頭をあげ、活々として粗っぽく強靭で狡猾なことを誇り顔に歌っている都市があったら、さあ見せてくれ」と、この都市の力強さを正面から受け止めているのだ。
『シカゴ詩集』が発刊されてからおよそ20年後の1935年、ル・コルビュジェは初めて訪れたニューヨークの摩天楼に大きな刺激を受けて、その紀行記ともいえる『伽藍が白かったとき』を著したのだった(1937年)。しかし、副題に「臆病人国紀行」を付し、あるいはまたニューヨークでのインタビューの第一声「ニューヨークの摩天楼はあまりに小さすぎる」が示すように、ル・コルビュジェは摩天楼、そしてアメリカ文明に「歓びと嫌悪」の両方を感じ取ったのだった。この書の中でもシカゴに触れている箇所が多いが、都市計画家・建築家の感性によって嗅ぎ分けたアメリカ都市文明について、詩人サンドバーグも同じように都市に潜む光と影を嗅ぎ分けていたのである。
【シカゴ詩篇】にある次の二つの詩も強く印象づけられたのだった。
ぼくの市の一番悪いところは何か、彼らはきっとこう言うだろう、
お前は小さい子供たちを太陽と露から遠ざけ、
でっかい空の下の草原にたわむれる明るい陽ざしや
痛快な雨から遠ざけてしまったことだ、しかも子供たちを壁と壁のあいだに閉じこめて、
パンと賃金のために、打ちのめされ、窒息しながらも働き、
二、三回の土曜日の晩にほんのわずかな給料をもらうために、
喉に埃を呑みこんで、心臓もからっぽのまま死ぬようにさせることだ、と。
昼間は摩天楼は煙と日光の中におぼろに聳え、たましいを持っている。
草原と盆地と大都市の街区が人々をそこに注ぎこむ、彼らは20階の各層に紛れこみ、また再び草原と盆地と街区に吐き出される。
このビルディングに夢や想念や記憶にみちた一つのたましいを与えるのは、ひねもすそこに注ぎこまれ、吐き出される男や女、少年や少女である。
(海に投げ出されたら、砂漠に留められたら、誰が、ビルディングに心ひかれ、その名を口にし、また巡査にそこへ行く道をきこうとするだろう?)
エレベーターは大索によって昇降し、管が手紙や小包を運び、鉄のパイプがガスや水を送りこみ、下水溝がそれを外に出す。
電線は秘密を抱いて上へと伸び、光を運び、言葉を運んで恐怖と利益と愛を伝える-事業の計画と取っ組む人々の罵言やら、恋のたくらみをする女が問いかける声まで。時々刻々、多くの潜函は地中の岩石に到達してこのビルディングを自転する遊星に固定させる。
時々刻々、大梁は肋骨のような役目を持ち、伸びて石の壁と床をしっかりと結びつける。
時々刻々、石工の手とモルタルは建築家が決めた形態に合わせて細かい部分を堅く締めつなぐ。
時々刻々、太陽と雨、空気と錆、それから幾百年かにわたる歳月の圧力は内からも外からもこのビルディングに働きかけて、これを消耗させるのだ。
杭を打ち、モルタルをこねた人々は、いま風が言葉もなく荒々しく吹きすさぶ墓地の中に眠っている。
電線を張り、パイプや管を敷設した人々や、ビルディングが一階二階と築かれていくのを見た人々もやはりそうだ。
そうした人々すべてのたましいがここにひそんでいる、そればかりか、いまは数百マイルも離れた土地で家の裏口に立ち、物乞いしているかつての材料運びの人夫や、酔っ払って人を射殺したかどで州の刑務所に入れられた煉瓦工のたましいも。
(一人の男は大梁からあしをすべらし、真逆さまに落ちて首を折った―その男はここにいる―彼のたましいはこのビルディングの石のあいだに入っているのだ)
各階にずらりと並んだ事務所のドア―そこにある何百という名前の、その一つびとつは、子供に死なれるとか、熱烈な恋をするとか、百万ドルの事業にたいして烈しい野心を燃やすとか、愚かにも安易な日々を送るとか、それぞれの人間の顔の代りになっているのだ。
ドアにかかっている看板の向うで彼らは働らいているが、仕切りの壁は相接する部屋に何も伝えない。
一週十ドルの速記者は会社の幹部や弁護士や能率専門家から手紙をうけ取り、また一方では幾トンという手紙が束になって、このビルディングから地球のすみずみまで送られる。
女事務員たちの笑いや涙も、このビルディングを支配するおえら方とまったく同じで、このビルディングのたましいの中に入っていくのだ。
時計の針が正午を指すと、各階から男や女が出はらって、外へ行き、食事をし、それからまた仕事に戻ってくる。
午後も終り近くなると、人々は一日が終わりかけていることを感じて、あらゆる仕事の調子がたるんでのろくなってしまう。
各階の一つびとつが空いていく・・・制服をきたエレベーター係もいなくなる。
バケツの音・・・外国語をしゃべりながら、掃除人が働いている。箒と水と雑巾棒がその日の人間のごみや痰や、機械の汚れを除き去るのだ。
屋上に輝く灯火が文字を綴って、何マイルにわたって家々や人々に、どこで金を出して買ったらよいかを教えている。この広告塔は真夜中まで語り続けている。
廊下のあたりは暗闇、声の反響、静寂の占めるところ・・・守衛がゆっくりと各階を歩きまわり、ドアの鍵をたしかめる。腰のポケットから連発ピストルがのぞいている。すみずみに鋼鉄製の金庫がおいてある。その中には金がずっしりつまっているのだ。
一人の若い守衛は窓に凭りかかって外を見ている、港を斜めに横切っている艀舟のあかり、駅の構内の網目のように入れ交った赤と白の無数のカンテラ灯、それから白の線や十字形と房状のにじみが所々に散っている、眠れる都市の上にかかるぼっと霞んだ夜空のひろがり。
夜は摩天楼は煤煙と星々の中におぼろに聳え、たましいを持っている。
【シカゴ詩篇】の最後の詩が「摩天楼」である。摩天楼が大規模な基礎工事やとび職人・建築職人などによって築き上げられる様をこのように具体的に描き出していることに感動すら覚えたものだった。そこにはそうした人々すべてのたましいが潜んでいるというのだ。そして聳え立つ摩天楼に毎日注ぎこまれ、また吐き出されていく勤労者の姿を見事に描き出している。
ル・コルビュジェが『伽藍が白かったとき』でニューヨークの摩天楼に抱いた光と影、その実態に迫る考察は、その20年ほど前に編まれたサンドバーグのシカゴ詩集「摩天楼」に相通ずるものがある。
【戦争詩篇】
この一年ブラッセルからパリに至る戦線で砲声がとどろいている。
それで、ウィリアム・モリス[1]よ、ぼくはあなたが書いた北フランスの寺院の大きなアーチや内陣や小さい奇妙な隅に関する古い一章を読んだとき―ブルル、ルル!
ウィリアム・モリスよ、あなたが既に死者であることをぼくは喜ぶ、あなたが湿った黴くさいところに埋められ、生きている者の代りに思い出があるだけなのを喜ぶ―あなたはこの世にいないことをぼくは喜ぶのだ。
ウィリアム・モリスよ、あなたは決して嘘を言わなかった、あなたはその積み上げられ、彫刻をほどこした石の形を愛して、職人たちがそれらに生の喜びを注ぎこんだ故に、夢想し感嘆したのであった。
前掛をつけた職人たちは槌をふるいながら歌い、また祈って、彼らの唄と祈りを壁や屋根、突出部や隅石や奇妙な樋嘴(ガーゴイル)に吹きこんだ―彼らの子供も女の接吻も、みのる小麦も花咲く薔薇も。
それで、ウィリアム・モリスよ、ぼくはあなたがこの世にいないことを喜ぶ、あなたが死者であることを喜ぶ。
この一年ブラッセルからパリに至る戦線で砲声がとどろいている。
ここで、突然、あのウィリアム・モリスが出てくる。
生活と芸術を統一させようとするモリスのデザイン思想とその実践(アーツ・アンド・クラフツ運動)は、建築を学ぶ学生たちにも大きな影響を与えたのだった。[2]
サンドバーグは、英国の詩人で生活の中の美、農村の風景などをこよなく愛し生活工芸運動を続けたモリスが第一次世界大戦の時期に生きていなくて幸せだったと言う。それはいうまでもなく、歴史上初めての世界大戦の悲惨さを訴えているのである。

【かつての日々 1900-1910】
ぼくは忘れないだろう、ブロードウェイよ、
お前の金いろに輝やき呼びかけている灯火を。
ぼくはいつまでも憶えているだろう、
高い壁に囲まれた雑踏と遊楽の河。
お前を知っている心はお前を憎み
お前に笑いを投げた唇は
生命とその薔薇を灰にして消え果てた、
お前のザラザラした踏石の埃の中に
消え去った夢を呪いながら。
ブロードウェイは大都会における賑わいの中心、大都市が創り出した歓楽と誘惑の場・装置である。それは必要悪なのだろうか?
ル・コルビュジェもまた『伽藍が白かったとき』の中で、ブロードウェイについて以下のように触れている。
「私はブロードウェイの眩い広告をだまって見のがすわけにはいかない。・・このすぐ目前の星座、人々を誘いよせるこの銀河は、しばしばくだらない娯楽に導くだけである。・・ブロードウェイの街でメランコリーといきいきとした華やかさとの分裂した感情にかられながら、・・彷徨った。」
ル・コルビュジェ『伽藍が白かったとき』
サンドバーグとル・コルビュジェはともに都市を讃え、そして都市の醜さや不合理を叩く。
1910年代は第一次世界大戦とそれによる経済の急成長をとげたアメリカ、そしてロシア革命とソビエトの成立、1930年代は世界大恐慌後の混乱とドイツにおけるナチズムの台頭など第二次世界大戦への足音が忍び寄ってくる時期であった。建築の世界では、1928年にCIAM(Congrès International d’Architecture Moderne、近代建築国際会議)が発足し、建築家たちも国際的な視野で都市・建築の将来について討論を重ねていった。きっかけは1927年の国際連盟本部設計コンペにおいて、ル・コルビュジエの計画案に対しボザール流の旧式な建築家が規約違反として排斥し、近代建築運動側と保守派の対立が表面化したことにある。グロピウス、ギ―ディオン、ミース・ファン・デル・ローエ、ル・コルビュジェらが参加してCIAMを設立した。1959年まで続いた国際建築運動である。
これらの時代背景の中で、ル・コルビュジェはもちろん、サンドバーグも都市に対する深い眼差しを注いでいた。彼らの透徹したメッセージが現代の都市に大きな影響を与えたかどうか、はなはだ疑問である。都市の将来を見定めていく者、都市をマネジメントする者は都市社会に生きる生活者ではなくなってしまった。行政も都市計画に主体的に関わっているとはいえないのではないか。最も大きな、肝を握っているのは大企業であり、資本家である。その流れは1985年プラザ合意以降金融資本の台頭によって、さらに世界の潮流になってきた。
『東京 世界都市化の構図』(青木書店、1990年)の「第5章 現代都市計画の展開と展望」を執筆した時に読み進めていた『転換期における人間 4都市とは』(岩波書店、1989年)の中の経済学者・宇沢弘文の指摘は、身震いするほどの衝撃だった。「日本の都市は遂に貧困化してしまった」(同書6ページ)、さらに「近代的な都市計画の考え方は、都市に住んで、生活を営む市民の人間的観点を無視するか、あるいは都市計画者自身のもっている画一的で、浅薄な人間像をそのまま投影したものであった」(同書17ページ)。
私はこの衝撃的な指摘に対して次のような見解を述べた。「都市の姿、とりわけ、わが国における大都市の姿は、経済と政治の最もダイナミックな投影である。プロフェッションとしての『都市計画者』が、いったいどこでどんな役割を果たしてきたのか、あるいはそれに固執できたかについては、宇沢氏の指摘するほど、イニシアティブを握ってきたとは思えない。他のほとんどの課題と同様に、『人間的観点』―別の言い方をすれば、資本の論理に対抗する『生活の論理』ということになろうか―が、大きな国民的合意に成長しなければ、彼らに多くを期待することはむずかしい。わが国には、さまざまなプロフェッションの専門性を絶えずチェックし、さらにその専門性を育てていくという市民的コンセンサスの土壌が形成されているとは言い難い」(『東京 世界都市化の構図』、166ページ)。
つまり、世界の都市活動は、庶民の暮らし(地域社会と生活)と行政や政治家たちによる行政・政治活動、そして最も大きな影響力をもつ経済活動(今日ではとりわけ金融経済)の三者のせめぎ合いの総体である。残念ながら宇沢の指摘する都市計画者は、行政や経済界の主導する場面で都市の将来像を描き出して見せる、そういう都市計画者である。今日の東京の姿とその変貌ぶりは、地域社会や庶民の生活の姿を消し去ろうとしているようにさえ見える。もちろん、このような権力的な都市計画に対抗し地域コミュニティや地域住民とまちづくりに取り組んでいる都市計画プランナーも数多くいる。この草の根からのまちづくりを育て上げながら都市計画の軌道修正に繋げていくことが有力な道のりなのかもしれない。
サンドバーグを読み、ル・コルビュジェに学び、そして現代の都市の姿に触れながら、都市計画・まちづくりの場面で専門家として関わるときに、都市のダイナミズムを時に感動し時に憎悪しながら都市の魅力を嗅ぎ分け、もちろん専門家としての倫理観を研ぎ澄まし、そして都市を動かしている非人間的な力に対抗していくことを統合していく営みが求められていることをあらためて再確認したいと思う。
詩集には安藤一郎が以下の訳者注を追記している
ウィリアム・モリス(1834-96)英国の詩人、工芸美術家、社会運動家、ラスキンの影響をうけて、中世趣味を持ち、生活の喜びと人生のための美を説き、芸術を実社会に結びつけることに努力した。
参考文献:藤田治彦 『ウィリアム・モリス 近代デザインの原点』(SD選書:鹿島出版会、1996年)など


最近のコメント