「建築」と「アーキテクチャ」邂逅の第一幕
“普通のものづくり産業”としての建築業
本書は、経営学・経済学を専門とする藤本隆宏らと、建築学を専門とする野城智也、安藤正雄、吉田敏らの長年にわたる共同研究の成果であり、建築業を“普通のものづくり産業”として分析し、得られた知見がまとめられたものである。
建築業は、きわめて特殊な産業であると見なされがちであるし、建築業のなかに身をおくわれわれ自身も、とかくその特殊性を強調するきらいがある。しかし本書には、建築業を一般的な製造業やサービス業と同様に扱おうとする冷静な態度が通底しており、したがって本書では、建築物もまた、自動車やコンピュータと共通する“普通の”人工物として取り扱われる。このことは、本書の冒頭で提出される一種の仮説なのであるが、その仮説がさまざまな観点から検証されるスリリングな展開が、読者を飽きさせないスパイスとなり、高度に専門的な学術書である本書を彩ることとなる。いうまでもなく、建築業を“普通のものづくり産業”として扱う態度は、「建築業は特殊である」との安易な結論によって思考停止に陥りがちな、これまでの建築産業論を強烈に牽制するものであるし、この態度自体が、書中で示されている数々の革新的な知見を導く源泉ともなっている。いずれにせよ本書は、その専門にかかわらず、建築業に携わる誰しもにとって、読むに値するに充分な内容を備えているというべきだろう。
アーキテクチャとしての建築
さて、本書の内容を紹介するにあたって、鍵となる概念をあらかじめ説明しておく必要がある。
第一に、本書は「広義のものづくり論」に立脚したものである。ここで「ものづくり」とは、“つくり手の意図である「設計情報」を「もの(媒体)」に転写し、あるいはつくり込み、顧客に伝達する行為の総体”であると定義されている。すなわち本書では、「ものづくり」が単に“原材料を加工して経済価値を得る”第二次産業の一形態であると捉えられることはない。「ものづくり」は、「設計」という無形の行為を通じて顧客満足を生みだす経済行為であり、その点で、無形の財(サービス)を顧客に提供するサービス業とも共通性が見いだせることが指摘され、このようにして「ものづくり」は、第二次産業と第三次産業にまたがる枠組みとして拡張されるのである。
このとき浮上するのが、無形の行為としての「設計」の重要性であるが、本書では、この「設計」という行為の対象であり、取引され対価を得るタイプの人工物である「製品」に対して、「アーキテクチャ」と呼ばれる見取り図が導入される。
「アーキテクチャ」とは、製品の設計構想のことを指し、より厳密には、製品が備える設計情報の抽象的・形式的側面であると定義される。設計情報は、製品の構造(物的な構成)に関するもの、機能に関するもの、工程に関するものなど、さまざまな情報要素から構成されるが、これらの情報要素(設計要素)は、製品の構造や機能、工程を定義するパラメータであると見なすこともできる。たとえば住宅は、屋根、壁、床、建具などといった構造要素の集合であると見なすことができるが、個別の構造要素である屋根は、見付け面積、勾配、屋根葺き材の材料とそのサイズなどをパラメータとして記述することができ、したがって住宅総体も、パラメトリックに表現することが可能である。あるいは同じ住宅を、遮音性能や断熱性能などといった要求される機能をパラメータとして、それら性能値の集合として記述することも概念的には可能である。
これらのパラメータ、すなわち製品の設計要素は、一般的には互いに連関する。たとえば屋根葺き材の材料と屋根勾配が連関することは、建築業に携わる者であれば常識であるし、屋根葺き材はそれぞれ固有の構法を持ち、したがってその工程も、ある程度は限定されることとなる。「アーキテクチャ」とは、こうした設計要素間の対応関係を抽象的・形式的に示す概念であり、設計要素を点、それら設計要素間の対応関係を線で表せば、網状の幾何学構造(グラフ理論で定義されるところのグラフ)を得ることもできる。また、これらの設計要素のうち、製品構造に関するもののみを取り出し、その対応関係を記述すると、製品の構造アーキテクチャを得ることができ、製品機能に関するもののみを取り出せば、機能アーキテクチャを得ることができる。同様のやり方で、工程に関する要素の対応関係を記述すれば、工程アーキテクチャを得ることができるが、個々の工程を線で、その対応関係を点で表せば、これは建築業でおなじみのアロー型ネットワーク工程表となる。
また「アーキテクチャ」は、これら設計要素のまとまりの階層構造として表現することも可能である。たとえば住宅という物的まとまりは、前述したように、屋根、壁、床、建具などの物的まとまりの集合体として見なすことが可能であり、この場合、後者のまとまりは、住宅という物的な全体構造の下位構造であると考えることができる。さらに屋根、壁、床といった下位構造に属する要素は、下地材や仕上げ材など、より下位の要素群から構成されると考えることができるが、これらの要素を点で表し、上位の要素と下位の要素の包含関係を線で表せば、全体構造という一点からツリー状に展開する幾何学構造を得ることができる。また、住宅の全体機能を“住まい手が長期にわたって安心して生活の中心としての拠り所となる”ことと定義すれば、その下位機能は、居住時快適性や防犯性、将来の生活の変化に対する追従性などとして展開することができ、物的構造の場合と同様に、全体機能から下位機能に至るツリー状の機能構造を記述することができる。
ここで、ツリー状に展開された製品の物的構造と機能構造について、それぞれの最下位要素どうしの対応関係に着目してみよう。製品によっては、物的な最下位要素(最下位の構造設計要素)と機能的な最下位要素(最下位の機能設計要素)が、一対一の対応関係を示すことがある。たとえばデスクトップ型のパソコンでは、本体は計算機能に対応し、モニタは出力機能、キーボードは文字入力機能、プリンタは印刷機能に対応するといった具合に、構造設計要素と機能設計要素がおおむね一対一で対応する。アーキテクチャがこのような特性を示す製品、つまり多くの部品が機能完結的な製品は、「モジュラー型」と呼ばれる。対して、構造設計要素と機能設計要素が多対多対応を示し、複雑に絡み合っているアーキテクチャをもつ製品は、「インテグラル型」と呼ばれ、自動車などがその典型とされる。具体的に見れば、自動車のボディは、“安全性・居住性・デザイン性・空力特性など、複雑な機能”を持ち、またこれらの機能は、タイヤやサスペンションやエンジンなど、ボディ以外の部品によっても担われているから、自動車の機能は、複数の部品が複合することによって発揮されると考えられるのである。
こうした観点から建築物を捉えてみると、その基本的な機能である雨仕舞いや耐震性などが、複数の部品や部材が複合して発揮されることからわかるとおり、建築物のアーキテクチャ特性は、インテグラル寄りとなる場合が多い。また、一般的にモジュラー型の製品では、各部品(モジュール)の設計者は、構造要素間の連結部分(インターフェイス)の設計ルールについて事前の知識があれば、“他の部品の設計をあまり気にせず独自の設計ができ”、インテグラル型の製品では、“各部品の設計者は、互いに設計の微調整を行い、相互に緊密な連携を取る必要がある”とされており、したがって“「モジュラー型」が、部品間の「摺り合わせ」の省略により「組み合わせの妙」を活かした製品展開を可能とするのに対して、インテグラル型は逆に、「摺り合わせの妙」で製品全体の完成度を競う”傾向があるという。すなわち、製品の特性を表現する概念として導入された「アーキテクチャ」は、その製品の母体となる産業の特性をも暗示するのである。
本書では、以上のような概念を議論のための基本的な前提としながら、建築業や建築物の構造が、「広義のものづくり論」に基づき読み解かれていく。いうまでもなく、ここでいう建築業や建築物の「構造」とは、「アーキテクチャ」にほかならない。本書の副題が、「Architecture as “Architecture”」(アーキテクチャとしての建築)とされている所以である。
日本の建築業のアーキテクチャの特性
本書は、序章と終章を全体の両端に据えながら、建築業や建築物を「ものづくり論」として読み解くための基本的な論点を整理した第I部「ものづくり経営学から見た建築」にはじまり、そこで提出された「アーキテクチャ」の概念を軸として建築物を捉えなおすとともに、日本の建築業の強み・弱みを浮き彫りにすることを試みた第II部「建築ものづくりの特徴」が続き、さらに第II部で明らかとなった日本の建築業の特徴を踏まえた上で、その現状に対する問題提起と提言を試みる第III部「建築ものづくりにおける課題と展望」で完結する構成となっている。つまり本書では、日本の建築業の産業論的分析による課題の明確化が、全体の核をなす部分として位置付けられているわけであるが、結論からいえば、日本の建築業の最大の課題のひとつは、“「価値実現」、つまり顧客満足と利益獲得が両立するような建物の供給価格と機能(サービス)のパッケージをいかに実現するか”であることが証されている。
では、建築物の「価値」とは何か。工業製品では多くの場合、“購入者は機能に対して対価を払う”とのロジックが認められるというが、建築物の価値も、その機能に見いだすべきであるとするのが本書の一貫した立場である。ただし、ここで機能とは、使い勝手のような狭義の機能にとどまらず、その美観や、使われ方の変化に追従するための空間的余裕なども、建築物の機能として捉えられている。そもそも本書では、“ある目的のために仕切られた「空間の供給」”そのものが建築物の基本的な機能であると位置付けられており、その意味するところは広範である。また、こうした建築物を含む人工物の機能は、その構造(物的な構成)から一意には定義されず、使い手みずからの操作により、“引き出される”側面があるとされている。すなわち使い手は、“そのプロダクトを手に取り、使ってみて、自分が使いやすいように機能を構成していく”ものであるとされ、機能が設計情報に落とし込まれ、「もの」に転写された結果、できあがった「もの」を使い手が使う過程で、自然発生的に構築される機能を「発生機能」と呼び、つくり手が設計時に想定した機能である「設計機能」とは明確に区別している。
本書でいうところの「発生機能」とは、「もの」と「使い手」とのあいだに定義されるアフォーダンスによって、事後的に創発される機能であると考えてもよいだろうし、建築物の基本的な「設計機能」が“空間の供給”にあるのだとすれば、建築物における「発生機能」と「設計機能」の関係は、アンリ・ルフェーブルがいうところの「表象の空間」と「空間の表象」の関係 [1] と同値であると見なすこともできるだろう。「発生機能」は建築物に限らず、“どのようなプロダクトについてもつくりだされる”ものであるというが、本書でも述べられているとおり、“建築物の構造(空間)と機能(用途)の関係は、通常の製品(たとえば自動車やコンピュータ)に比べれば、流動的で創発的”であり、“それが利用される場面で想定外の機能が事後的に発生することがある”のが建築物の特徴である。したがって建築物は、その使用が開始される前には必ずしも機能が明確ではなく、“機能に応じた価格を決めることには、根源的な難しさがある”。このことが、建築物の価格が機能に応じて決められず、むしろ価格とコストが混同されている状況の一因であることを、本書は指摘している。
ただし、価格とコストの混同は、日本型の建築業の特性と大きくかかわっているとの指摘も、見逃すことはできない。日本は設計施工一貫方式という、国際的に見ても特異な調達方式が発達した国であるが、この方式は、受注者(ゼネコン)がインハウスの設計者を大量に抱え込み、本来は発注者の指示に基づき、設計者がまとめあげるものであるはずの機能設計を肩代わりし、発注者からの要求機能があいまいな状況下でも、積極的に発注者のための価値創造に携わることによって、発注者からの信用を増すのに有効であったという。取引にあたって信用が重視され続けてきたのは、日本が長期にわたって、継続的な発注が期待可能な建設市場の成長期を謳歌していたことによるわけであるが、その慣行は、市場が衰退期に入った現在まで継続し、結果として日本型システムは、“発注者による受注者の選別という競争的市場の要件が十分に成立しないまま今日に至っている”のである。
また、このような日本型のシステムは、日本の建築業に独自の性格を備えさせる方向に働いたことも、本書は鋭く指摘する。すでに述べたとおり、建築物のアーキテクチャは、他の製品に比べてインテグラル寄りの性格をもつ傾向にあると考えられるが、機能設計を工事の請負者であるゼネコンが肩代わりすることは、建築物の物的構造を摺り合わせ、コスト削減を実現できるというメリットをもゼネコンにもたらし、結果として日本の建築物のアーキテクチャは、よりインテグラルな性格を強めることになったというのである。さらに本書は、こうした日本型システムの特性が、設計図書の完成度の低さや設計期間の短さ(設計段階での仕様の確度の低さ)、設計料の不十分さ、部品や部材間の相互依存性が高い構工法など、日本の建築業の随所に影響を及ぼしていることを、丁寧に紐解いている。
建築の多様なアーキテクチャ戦略とその読み解き
以上のように、日本の建築は、その発展の経緯からして、他国と比してもより強いインテグラル型(摺り合わせ型)のアーキテクチャを持ち、統合型の組織能力を発揮しやすいことが特徴であるという。このことは、日本型ものづくりに広く観察できる特徴であるし、また同時に、日本型ものづくりのひとつの強みであったと考える向きもありえるだろう。ただし、製品のアーキテクチャが市場において強みをもつか弱みをもつかは、みずからの製品や組織の特徴ばかりでは必ずしも定まらず、“市場ニーズの特性、あるいは社会的・技術的な制約条件を前提として”アーキテクチャの戦略は組み立てられるべきとの議論が、本書では展開される。日本の建築業に見られるようなインテグラル型のアーキテクチャをもつ製品でも、それを“汎用的な「標準品」として販売する場合”と“「カスタム設計品」として売る場合”では、競争戦略のポイントや利益率も異なる場合があり、たとえば前者の場合、“市場シェアの獲得によるコスト優位が至上命題になる”が、後者の場合は“優位な価格設定ができるか否かが重要になる”という。このようなアーキテクチャの戦略上の定石を、本書は「アーキテクチャの位置取り戦略」として論じているが、その過程で、戸建て住宅、分譲マンション、賃貸オフィス、病院などといったビルディングタイプの特性、あるいはリフォーム・リニューアル市場、海外市場などといった市場の特性に応じて、アーキテクチャの位置取り戦略が異なることが明らかにされている。すなわち、建築のアーキテクチャは通り一辺倒なものではなく、多様なものでありうるし、建築業の組織戦略も、さまざまでありうるといって良いのだろう。本書は、こうした議論を延長することによって、最終的には日本の建築業の展望について論ずるに至る。その核心部分は、本書を実際に手に取って確かめていただきたいが、この書評では、どちらかといえば未来の建築業に向けられた本書の内容が、過去の建築業の見取り図を描くにあたっても有効であろうことを、最後に指摘しておきたい。
本書の執筆者である藤本はかつて、共著者として参加した『モジュール化』と題された書籍 [2] において、産業のモジュール化、つまり製品を構成する部品の独立した主体による半自律的生産が成立するための要件を、製品のアーキテクチャの観点から論じているが、ここで主題とされている産業の「モジュール化」は、建築業においても重要な課題として位置付けられた時期があった。すなわち、第二次大戦後の建築生産の工業化が推し進められた時期であり、建築学における代表的な議論として、内田祥哉らによる「オープンシステム理論」[3] などを挙げることができる。日本における建築生産の工業化は、必ずしも内田らが意図したとおりには着地しなかったが、産業や製品のアーキテクチャ論には、オープンシステム理論と重なる部分も多々見受けられ、またかつての建築学における議論をより発展させた内容も含まれており、内田のもとで学び、建築構法計画学に立脚点を持つ野城や安藤が、建築をアーキテクチャとして論じたことは、必然的な帰結であったと見ることもできる。
ところで、建築生産のオープンシステム化、あるいはモジュラー化に関する議論は、1960年代頃には国際的な拡がりを見せていたが、これらの動きがモデルとしたもののひとつとして、江戸時代末期から大正時代中頃までの日本の木造建築の生産システムを挙げることができる。前掲書で藤本らは、産業のモジュール化の要件のひとつが、モジュラー型の製品アーキテクチャを実現することにあることを明らかにしているが、当時の木造建築の体系も、まさにモジュラーなアーキテクチャを有していたと考えられ、本来的にインテグラル型の性格が強い建築業において、モジュラー型のアーキテクチャが成立した背景には、産業論としても大変に興味深いところがある。また、各国での建築生産の工業化に関する理論的追求が、必ずしも成功につながらなかった要因も、近代建築産業論として十分に研究に値する。本書で示された「アーキテクチャとしての建築」という枠組みは、こうした過去の建築産業を史的に描写するにあたっても、きわめて有効な武器として力を発揮するだろうことが期待でき、その意味で、「普通のものづくり論」として建築業を論ずることは、より広範な展開を見せる可能性を秘めていると考えられるのである。
アンリ・ルフェーブル『空間の生産』(斉藤日出治訳,青木書店,2000年)
青木昌彦,安藤晴彦(編著)『モジュール化 -新しい産業アーキテクチャの本質』(東洋経済新報社,2002年)
内田祥哉『建築生産のオープンシステム』(彰国社,1977年)


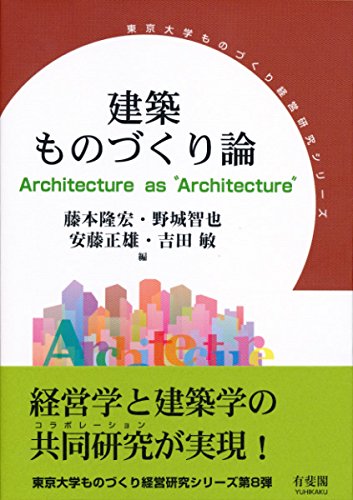
最近のコメント