日時:2015年7月7日(火)18:30~20:30
会場:東京理科大学神楽坂地域デザインラボ
ゲスト
鈴木明
太田佳代子
司会
宇野求
1 建築雑誌『telescope』を発刊するに至った動機 [1]




宇野 今日ゲストのお二人と僕は、ほぼ同世代です。僕らが建築の仕事をしてきた30年ほどを振り返ると、日本と世界の関係、内外の建築界のあり方、関係が大きく変わりました。鈴木さんと太田さんが共同で発行していた媒体『telescope』を話題としながら、その前後の時代、日本内外の建築界が、どのように変わってきたのか? そうしたことについて話しを進めていけたらと思います。
二人は違う舞台で違うキャリアを積んでいたので、『telescope』を二人で出しはじめた時、どうして?って思いました。『telescope』を始めたのは、どういうことがきっかけだったのですか?
太田 わたしの場合は非常に単純で、当時、あまたあった建築の専門誌も含め、建築本来の楽しさと建築業界での言説とのギャップにフラストレーションを感じていた、というのが背景にありました。それまで私は黒川紀章さんのアシスタントとして国際会議の立ち上げとかグループ展なんかのオーガナイズを担当していたんですが、そういう仕事のなかで特に若い世代の建築家と話していると、ある種の狭さが気になってきたんですね。ちょうどバブルの時代で、一見やりたい放題な時代なのに、逆に丹下健三や黒川さんたちメタボリズムの方が社会全体に対してはるかに強烈なメッセージを送っていた。当時はまた、難解な表現を操るのがトレンドだった時代で、それが建築の空虚さにストレートに繋がっていると感じてました。まあ、そんな違和感が膨らんでいくうち、いつのまにか新しいメディアの可能性が見えた気がしたわけです。
宇野 どうもありがとうございました。では、鈴木さんも同じように、ことの起こりについてお話しお願いします。
鈴木 僕は武蔵野美術大学に入り、大学院まで行って建築の勉強をしました。卒業後、『新建築』の編集部で7年間仕事をしました。
『新建築』は見てもらえばわかると思いますが、編集部の人は文章を書かないんですよ。建築家がしたこと、やったものに対して、色々な加工をしないというのが『新建築』の在り方でした。記録に徹する方針だったんです。一方で海外の雑誌を見ていると、『AA』(L’Architecture d’Aujourd’hui) とか様子が違うし面白いなと思っていたんです。大学の校風もあって実際に編集の実務に関わる前に海外の雑誌には親しんでいたと思います。一番読んでいたのは『AD』(Architectural Design)というイギリスの雑誌です。そういう状況の中で育ってきて、先ほど太田さんが若い世代の建築家は話が面白くないって言ってましたが、僕も角度は違うんですけども、『新建築』に入ったら同じようなことを感じていました。それでこれは自分でやるしかないのかなと考えるようになりました。

2 『telescope』を通じた海外の建築界との交流
宇野 いま二人からお話し頂いたのは『telescope』前史ですね。では二人が一緒にやろうよ(新しい媒体をつくろうよ)と言ったきっかけは、どんなことだったんでしょうか?
鈴木 私としてはやりたいことが三つくらいありまして、一つは雑誌を作りたいということ。それともう一つは教育をやりたい。教育っていうのはいわゆる大学の教育ではなくて、学生というよりも社会に出た若い建築家が気楽に参加できる教育のシステムがあってもいいんじゃないかと。それから、もう一つは、国際化みたいなことですね。若い建築家が外国で起こっているような事や建築の大学で起こっているような内容の教育を受けられるような、そういう組織を作りたいと。『telescope』は媒体の名前で、「建築・都市ワークショップ」が組織の名前です。
宇野 『telescope』は、僕も創刊号から何号か持ってたんですけど、何か面白いものが出来たなと思って、何度もパラパラ開いて眺めたりしてました。『telescope』は、何かもとになったものってあったんですか?ああいう媒体は日本には全くなかったじゃないですか。
太田 1981年頃でしたか、ピーター・アイゼンマンが主宰していた IAUS(Institute for Architecture and Urban Studies)というオルタナティブな建築研究機関が『スカイライン』という雑誌を作ったんです。アメリカでももうほとんど手に入らない幻の雑誌で、タブロイド判でした。IAUSは、アメリカの既存の大学システムから外れた所で新しい教育をしようと、アイゼンマンが同世代の建築家たちと組んでニューヨークに創った組織で、そこがオルタナティブな建築雑誌を始めたわけです。残念ながら3年か4年位で終わっちゃいましたが、いまでも多分、私が一番好きな建築雑誌です。とりわけ面白かったのはアイゼンマンが聞き手の白熱インタビューで、一番強烈に残っているのがアイゼンマンvsレオン・クリエの延々と続く丁々発止。もうケンカに近いんですが、二人ともユーモアのセンスが凄いから滅茶苦茶テンション高くて。強烈な表現もありながらカットなしのやりとりに引き込まれるのは、建築の根幹に触れる、お互いに魂をかけた戦いをしていると思えたからでしょう。いやはや、すごいなこれはと思って。建築にもこういうメディアがあり得るんだ、とショックを受けました。
宇野 当時、日本内外のある種の状況が、建築界がつながり内外が反転する、そういう所に来たからだと思いますけれど、『telescope』がとてもユニークだったのは、人と人の直接の交流をつなげる媒介にもなっていた点でしょう。そこがすごくユニークだったと思います。
太田 じつは去年のヴェネチア建築ビエンナーレ日本館展示のために中谷礼仁さんと新しいタイムラインを作ったんですね。磯崎新の個人年表なんですが、日本の建築界の変動と国際化に彼がいかに関わっていたかが見えてきた。鈴木さんと私がやっていた「建築・都市ワークショップ」の位置付けも初めてわかりました(笑)。磯崎さんについてちょっと説明しておくと、彼は一建築家でありながら、いわば社会を相手としたキュレーターとして若い建築家たちを社会に組み込ませていった。これもバブル時代のことですが、たとえば「くまもとアートポリス」を立ち上げ、住宅より大きなものを手がける機会に恵まれなかった若手や外国人を、自治体の公共建築の設計者に採用していったんです。「くまもとアートポリス」はいわば、まちづくりとか公共建築の設計者選定の仕組みに風穴をあけようとする試みですよね。鈴木さんと私はそのころロンドンのAAスクールの校長だったアルヴィン・ボヤースキーにアプローチして、日本でAAの夏季スクールを開くことになり、それでザハ・ハディッドやナイジェル・コーツやダニエル・リベスキンドといった「アンビルト」とレッテル貼りされていた建築家たちが急に来日し始め、その動きが磯崎さんと繋がって小規模の建築を日本で建てる人も出てきた…。
宇野 僕のイメージでは、小さな媒体だったけれども、『telescope』を媒介として色々な事がひっくり返って、内外が本当の意味での交流を始めたと思います。僕らの世代からするとおさらいだけれども、学生からすると知らない、大切な現代史ですね。
60年代はじめに、丹下健三さんがアメリカにアピールしようとしていました。素晴らしい仕事はしてて、でもそれを世界に知ってもらおうという努力を、彼がやり始めて、その直下に黒川さんと磯崎さんがいました。今の太田さんの話しの流れで言うと彼らは、別の形で、丹下さんを見習ったんだと思います。結局のところ、この3人が人的交流と欧米の主たる建築のシーンとの接合を果たしたんだろうと思います。
ただ、僕らの世代以降、そして今の学生世代になると尚更だけど、当時よりはるかにダイナミックで、フレンドリーな、色々な形での国際交流があって、それからすると、今名前が出たお三方の巨匠のアプローチは、やや前の時代のやり方だったといえるかもしれない。対して、鈴木さん、太田さん、お二人がやってきた活動は、もっと日常的で人対人の付き合いも含めて現代的だなと思います。お二人はそれぞれ教育やキュレーションの仕事をされてきましたけれど、そうした仕事は、巨匠が日本の内外をつないできた時代とは別の独自性があるんじゃないかと思います。
鈴木 先日公開された石山友美さんの作った映画『だれも知らない建築のはなし』を観ていても、この表を見ても思うのは、磯崎さんも中村敏男さんも(当時)アメリカにしかネットワークを持っていなくて、当時の日本での外国の建築の紹介のされ方を見ると、とても偏っていたのではないかということがわかります。磯崎さんが付き合っていた建築家はあくまでも同世代だったんですよ。磯崎さんはその世代を長い間引っ張っていたんじゃないかと思いました。
一方で、僕らはAAスクールの学長さんだったアルヴィン・ボヤースキーとお付き合いすることになって、その下の世代、つまりアーキグラムの世代より下の世代にダイレクトに付き合うようになった。レム・コールハースより年下のリベスキンドやザハもそうなのですけども、その世代は当時磯崎さんが付き合ったことのない世代だったんですよ。

3 海外から見た日本の建築について
宇野 世界から日本の建築を見た時にどう見えるのかを考える時に、「P3会議」に焦点を当てたのはなかなか面白いアイデアだなと思いました。
太田 「P3会議」に焦点を当てようと考えたのは中谷さんなんですが、あの映画に出てくる「P3会議」のエピソードで私が特に思ったのは、日本と外国のお互いへの視線はずっとすれ違ってきたんだなあと…。私は2004年から3年ほどイタリアの建築雑誌『DOMUS』の編集をしていましたが、ミラノの編集現場でも日本の建築家の作品だけは優先的に扱われる傾向があって、日本人として逆に違和感を覚えたほどでした。
それは純粋に日本に興味や敬意を持っているというより、もっと単純かつ根が深いと思うんですよ。西欧における建築への退屈や諦めが、日本への憧れにすり替わっているにすぎない部分もあるのだと思います。そこを見逃したくないですよね。
鈴木 ひょっとするとレムが映画の中で「P3会議」に参加した日本の建築家について「オーラがある」と揶揄していたのは、そのような日本の建築家がつくるものがある種の理屈が付かないということも含めて言ったのかもしれないですね。
宇野 ヨーロッパの人たちは論理があるのが建築だっていう考え方がありますからね。
しかしここ半世紀において日本は50-60年代の「富士山・芸者」、70-80年代の「間」、近年では「かわいい」、と理屈では説明されないプレゼンテーションを行い、それが新鮮に思われて、不思議に感じられるから、面白いとか美しく誤解してくれたりしてたけど、この先は通用しないように私は思います。
太田 確かに明快に説明して理解を得ることは必要だと思います。ただ、リサーチし尽くし議論し尽くした末に辿り着いた解が、必ずしも面白い、必ずしも人の心を打つものになるとは限らない、と思うんですよ。建築には言葉では表現しきれない凄さとか力というのがあって、それによって美しくなったり厳かなものになったりもするわけですよね。おそらくレムもそれをよく理解していて、日本の建築家は何言ってるか分からないことも多いけど、彼らが創り出す建築の美しさをそのことと混同してはならない、という自覚も持っていると思うんです。
一方、日本人のほうは海外の評価を真に受けて、今の日本の建築は素晴らしいんだ、っていう風に単純に思い込んでしまう向きもあるように思いますが、それだといずれ消費されて終わりでしょう。私たちが『telescope』を創りたかった動機はそういうことも含めて風通しをよくしたい、遠くからの視点を近づけてみよう、ということでもあったんですね。
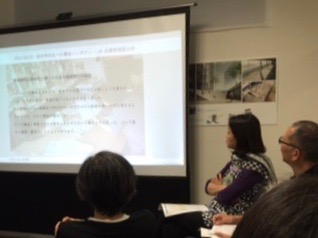


telescope(建築雑誌 1986-1995)
『建築都市ワークショップ』(鈴木明、太田佳代子 共同主宰)が、1986年に創刊した建築メディア。鈴木、太田による編集発行で第10号まで出版された。ポストモダン状況にあって多様な建築活動を展開していた当時の日本国内建築活動を海外に紹介すると共に、日英2カ国語の媒体として内外建築家の直接のコミュニケーションが図られた。1980年代初期、建築家ピーター・アイゼンマンがニューヨークのIAUS (Institute for Architecture and Urban Studies) で創刊した『SKYLINE』にならい、従来の建築雑誌の構成にとらわれない自由な編集方針がとられ、建築家や歴史家のインタビュー、セミナー、展覧会などから、建築と都市の文化をめぐるラディカルな討議を掲載、日本と欧米の建築設計界に新風を送り込んで先鋭的なインパクトを与えると共に、内外の建築状況を反転させる役割を果たし一世を風靡した。『telescope』独自の特徴として、国際的な若い建築家を中心とする新しく自由な建築教育への関心をあげることができる。ロンドンのAAスクール校長アルヴィン・ボヤースキーとの知己を得て、当時AA講師陣であったナイジェル・コーツ、ザハ・ハディッドらを招いたり、初来日したレム・コールハースやダニエル・リベスキンド、コープ・ヒンメルブラウなど、海外の若手建築家を多数日本建築界に紹介、国際プロジェクトのコーディネートなど、内外の人的交流の媒介の役割も果たした。1995年阪神淡路大震災を撮影した写真家宮本隆司の写真集が、最終号(第10号)。





最近のコメント